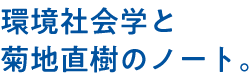Webデザイン
このWebサイト。もちろん、絵心がない僕がデザインしたわけではない。餅は餅屋である。プロにお願いした。
僕からデザイナーへのリクエストはいたって単純。載せたい情報はこれとこれとこれ。トップページには「環境活動の『見える化』ツール」をおきたい。なるべく親しみやすいページにしてほしい。少しだけ僕の研究活動について話した。打ち合わせに要した時間は10分か15分ぐらいだった。
後日、送られてきたデザイン案を見たとき、「プロだな」と唸った。僕の研究活動が伝わるデザインとして表現していたからだ。
とても気に入った。ただ、ちょっと柔らかすぎる気もした。「もう少し直線的な案もみたい」とメールでリクエストすると、まったく違うものが提案された。どっちも気に入ってしまった。迷った。どうしよう。けっきょく直感で決めた。後から提案されたのが今のデザインである。僕からのリクエストは短くシンプルであったため、説明不足で迷惑をかけたと思う。
地球研の飲み会でのこと。ある若手研究者から「菊地さんはデザイナーと協働したほうがいいですよ」といわれたことがある。僕の仕事を違う表現で伝えていったほうがいいという趣旨だったと思う。「自意識過剰系のデザイナーとは特に相性が悪いんだよね」と返したように記憶している。「俺が」「私が」と自分のアイデアやデザインを強いてくるデザイナーは、どうも苦手なのである。
勝手な想像そして浅はかな理解であるが、自分の内なるものを表現する人が芸術家だと思っている。その作品は商売になることもあるが、ならないこともあるだろう。それに対してデザイナーにはクライアントがいる。クライアントの話をよく聞きながら、でもクライアントだけでは表現できないものを創っていく。デザイナーは、協働作業をする仕事なんだと思う。ここでは、デザイナーの「私」は少し後ろに引いている。でも「私」が表現されていないわけでもない。
「研究対象者」といわれる人びとはたんなる対象者ではなく、一緒に考える存在と考えれば、研究者もデザイナーに似ているかもしれない。もちろん「対象者」はクライアントではない。一般的に研究者の方が、力が上のことが多いだろう。だから単純に比べることはできない。でも、人びとの話をよく聞きながら、人びとだけでは見えないものを見えるようにしていく。そして人びとが使える知的資源としていく。こうした協働作業は、研究活動のなかにいろいろとあるはずだ。そこから研究者はいろいろなことを学んでいるはずだ。こういうと「研究とはもっと崇高なものである」「御用聞きみたいなことは研究ではない」と怒られそうだ。
こんなことを書いている僕は「自意識過剰」なのかもしれない、です。