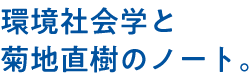第10回 いしかわ生物多様性カフェ(3/27)開催報告
開催日時:2025年3月27日(木)18:30〜20:30
開催場所:石川県立図書館研修室
話題提供者:野村 進也さん(いしかわ自然学校インストラクター・金沢大学連携研究員)
テーマ:身近な里山の生物多様性−生きもの調査体験から
参加者数:29名(一般参加者22名+スタッフ・関係者7名)
【話題提供】
自己紹介
私は関西生まれの横浜育ちで、2008年から石川県に来ました。ゲンゴロウの研究をしたいといったら能登を紹介されて、それから石川県に住み続けています。ゲンゴロウという名前は知っていても実物を見たことない人がほとんどだと思います。ゲンゴロウは国内に130種類以上、石川県では40種類以上記録されています。シャープゲンゴロウモドキとマルコガタノゲンゴロウ、この2種は全国的にも種の保存法という法律によって無許可での採取、譲渡、飼育が禁止されています。そういうゲンゴロウが実は石川県にいるんです。もともとは、ゲンゴロウのことをやるために石川県に来たのですが、身近な田んぼとか池とかで何か生きものを見せられないかという相談をよく受けるようになりました。そういうことを引き受けているうちに、観察会が自分の重要な活動になっていました。学校であったり、地域の団体であったり、この地域の生きものを見せたりしています。私はゲンゴロウだけしか知らなかったのですが、なし崩し的に、トンボ、カエル、淡水魚、川虫といった水の生きものを何でもやるようになっていきました。こうした生きものは里山の生きものなので、里山の生きものも含めて活動をしています。里山の生きものを通じて生物多様性とはどんなものなのか、人の活動とどうつながりがあるのか、そんなことをお伝えする活動をさせていただいています。
金沢市でやっているサイガワリバーサイドアクトという毎年犀川でやっている活動です。生きもの観察とかいうより、河川敷を使っていろいろな催しですが、その一環で生きもの観察をしたら、けっこう親子が来てすごく盛り上がってくれました。あとは調査業務もしています。生きもの調査を手伝ってほしいとか、生きものの標本の同定をしてほしいという依頼もくるようになりました。
里山の生物多様性ですが、里山はもともと人が適度に手を加えることで生物が維持される環境です。希少種が分布する地域の5割以上が里山と言われていたりします。里山って大事なんだよね、という話はありますが、ではどうやって伝えたらいいのか。学校の先生も、生きものや自然のこと、里山のことをテーマにした授業でしたいといっても、よく分からなかったりします。そういう時はご相談いただいて、子ども相手にお話をすることもありますが、自分が一番得意なのは、現場に一緒に出て生きものを集めてみましょう、どんな生きものか観察してみましょうという活動です。外に出る格好してもらって、長靴履いてきてもらい、網を持ってもらって生きものを集めてもらいます。見つかった生きものについて後でまとめて、こんな生きものがいた、ここはどんな環境なのかについて学んでもらいます。
珠洲市の小学校で、田んぼを使って観察をした時、珠洲でも町中の子どもだと田んぼに入ったことないって子が意外といたんです。せっかくの機会なので田んぼに入って生きものを見てみようかとやると、カエル、たとえばトノサマガエルは割と普通にいる感じですが、実は環境省の基準では準絶滅危惧種です。ほ場整備に弱いって言われています。またドジョウのような魚が出てきます。これも身近な生きものとされていますが、今の田んぼは、こういった生きものにはちょっと厳しい環境が増えています。そうであっても、観察した時に初めてドジョウとかカエルとかいるんだと、みなさん驚くぐらいの生きものが見つかったりします。または、田んぼといえばの生きものの一つのアキアカネ含めた赤とんぼが見つかったりします。「今でも赤とんぼいるんだ」という声も聞かれたりします。
生きものがいる環境
こうした生きものがいっぱいいて「いいね」という話だけではなくて、こういった生きものがいる環境はどんな環境なのかと考えていただきます。赤トンボで一番メジャーなアキアカネは田んぼの生きものとされていますが、具体的に田んぼをどのように使っているのでしょうか。アキアカネの話をすると、秋をイメージする方が多いです。夏とか春終わりごろとかにトンボを見せると、「え、トンボいたの?」とか「これ秋の生きものじゃないの」とか言われたりします。しかもアキアカネという名前ですが、田んぼで夏ごろに成虫になっています。
アキアカネが田んぼに来るイメージの秋には産卵していますが、卵は田んぼで越冬して、春ごろに田んぼに水が入った時に幼虫がそこで育ちます。その後、初夏にもう成虫になっています。つまり、全然秋とは限らないのです。ただ、その後アキアカネは、暑いのが苦手なので、標高の高いところに移動して夏を過ごした後、秋になって田んぼに下りてきます。これが風物詩的な、アキアカネのイメージを形成していると思います。こんな生活史を持っています。
このように、田んぼのスケジュールに合わせた生き方をしている生きものが結構います。田んぼはある時期水が入って、ある時期水がなくなる環境です。こうした環境に適応する生きものも多いのです。水の生きものの話をしていると、ずっと水があるといいように思われることがありますが、必ずしもそうではありません。こうした田んぼに来る生きものは、ある時期水が入った時に集中してそこに集まってきて、繁殖終わった後に別のところに移動するサイクルを持っている生きものが結構多かったりします。幼虫が育つ6~7月ぐらいまで水があれば何とかなるという生きものなんですね。アキアカネに限らず、似たサイクルをしている生きものをこの後紹介します。ただ、最近の田んぼは、石川県では6月ごろから中干をして、結構カラカラになっています。水が抜かれると、トンボはそこでなかなか育ち切れなくなることがあります。トンボから田んぼがどういう環境かということが見えたりします。
さきほど、トノサマガエルは準絶滅危惧という扱いになっているとお話ししました。アマガエル、シュレーゲルアオガエルなどは、指先に吸盤を持っています。窓とかにカエルがぺたぺた張り付いていたり、夜の自販機に登っているのを見たことがあるんじゃないでしょうか。こうしたことができるアマガエルと違って、トノサマガエルは吸盤を持ってないので、コンクリートが打ち込んであると上がれなくなってしまいます。したがって、ほ場整備によってコンクリート化されてしまった田んぼでは減ってしまうんですね。近代化は、田んぼをする方にはどうしても必要だと思いますが、生きものにとってはいろいろな影響があるということが見えてきます。
モリアオガエルについては、木から卵をぶら下げてオタマジャクシが下にぼとぼと落ちてくるイメージがあると思いますが、意外と田んぼの中で直接卵産んでいることがあります。モリアオガエルの産卵は5月から6月くらい、他のカエルに比べると少し遅いので、その時期に田んぼに水がないことが多かったりします。そういう影響がない場所だとモリアオガエルがに来てくれる可能性があります。
3月ごろからニホンアマガエル、ヤマアカガエル、今の時期に田んぼへ行くと、つぶつぶ状の卵があると思います。4月から5月ごろの田植えが近い頃には、アマガエル、シュレーゲルアオガエル、トノサマガエルなど、別のカエルがやってきます。6月ごろ大きな田んぼでは中干しで水が落ちるので、その時期までに他のカエルはオタマジャクシの時期を何とかクリアするか、もしくは何とか残った水のところに集まってやり過ごします。ただ、その時期にも実は水が残っていて、モリアオガエル、比較的繁殖時期が遅いツチガエルも田んぼに来ることがあります。カエルから見たら、田んぼだけでもこんなことが言えたりします。
次に水生昆虫です。オオコオイムシ、ヒメゲンゴロウ、マダラコガシラミズムシ、コウベツブゲンゴロウ、なかなか聞いたことない名前が多いと思いますが、こうした生きものがいっぱい来ます。しかも、こうした水生昆虫にも繁殖のために田んぼに来るものがいます。小さい時に来るんですよね。もちろん成虫もいます。水生昆虫にとって、カエルにとって田んぼはとても重要な場所なわけです。生きものにとって、田んぼと周りの水がちゃんとつながっているかどうか。たとえばメダカだったり、もっと大型のコイですら地域によっては田んぼに入ってきます。水伝いに移動できれば、いろいろな魚が田んぼにやってくる。雨になると水たまりにアメンボが来ているのを見たことある人もいると思いますが、ゲンゴロウは自分で行き来するし、カエルは当然陸地伝いに移動する。トンボの成虫は周りの森とかに来たりします。
つまり、田んぼの生きものは田んぼだけではなく、他の水場とかなり関係があるということなんですね。田んぼを田んぼだけではなく、一つの水系として周りの環境をワンセットで考えたほうが、いろいろな生きもののつながりが見えてくると思います。
田んぼをやる方には歓迎されないと思いますが、イナゴの仲間がいます。イナゴは2種類石川県に生息しています。コバネイナゴとハネナガイナゴです。ハネナガイナゴは石川県ではレッドデータに入っています。害虫と思われますが、ハネナガイナゴは少なかったりします。田んぼで捕って食べた方もいるんじゃないでしょうか。私も試してみました。
東京のレストランから、イナゴを捕って送ってほしいという依頼がありました。最初は石川県で捕っていました。能登はたくさん生息していそうなイメージでしたが、「田んぼ、イナゴなんかそんないっぱいないよ」「あんまりいないよ」って言われて。効率が悪かったんですね。ところが別の仕事で富山に行った時に田んぼ見たら、イナゴがすごい揺れるぐらい、跳び出していました。当時は能登に住んでいたのですが、富山まで行ってでも集めたほうが効率がいいという結論になりました。
イナゴの集め方は、夜中に耕作放棄地とかでヘッドランプ付けて、手でがーってすくって集めます。最初は網振って捕っていたのですが、どうも体力は使うわ、網はすぐ破損するので効率がよくないって気付きました。むしろ手づかみでやるっていう。しかも夜中ですから、ちょっと怪しいですよね。しかも手がイナゴ臭くなるっていう、めったにない経験しました。ちなみに依頼してきた東京のレストランに、帰省ついでに行ってみようと思って調べたら、ランチで万超えていました。
さらに、ハネナガイナゴがいますが、石川県で少ないと言われていましたが、意外といたりするのかな。農業試験場の調査で、どうもJAごとの農薬が影響しているということが報告されていましたね。イナゴを捕ってみると、いろいろな田んぼと農薬の関係も見えてくるかもしれないですね。
ほ場の周辺に水路があれば、やっぱり魚であったり、貝とかがいたりします。ヤリタナゴがいたりホクリクジュズカケハゼという石川県のレッドデータ入っているハゼが意外な水路で簡単に見つかったりすることがあります。さらに、二枚貝の仲間が住んでいることがあります。それぞれつながりがあるんです。タナゴの仲間は二枚貝を産卵場所に利用する。さらに二枚貝の子どもは、ヨシノボリのエラに寄生して生活しているんですね。共生ではなく一方的な利用なんですけど。ヨシノボリがいなかったら、この二枚貝はそこで生息できない、二枚貝がいなかったらそこにタナゴは生息できない、そんなことも言えてきます。水生動物同士でも利用し合っているとか、一方的に利用している。
したがって、ほ場を含めたこうした水系は、それぞれ独立はしていますが、同時に一つのまとまった環境としても見ることができるのではないでしょうか。田んぼは一時的に水が入る浅い場所、ため池はずっと水が残るけど、池干しという管理でたまに水が抜かれることもあります。川はずっと水が流れている。その周辺のそれぞれの環境に適応した生きものだったりするんですよね。アキアカネみたいなトンボは、幼虫の期間が結構短くて、1~2カ月とかそのぐらいかなと思ったら、逆に川にいるトンボなんかも幼虫の期間何年間もかけてじっくり成長するものもいたりします。そこに合った生きものがいたりするんですよね。
当然、水が増えたり減ったりします。たとえば「池の水ぜんぶ抜く」という番組があります。池の水を抜いて外来種を捕っています。あれをやると外来種だけではなく、プラスマイナスで長い目で見ると生物多様性にもプラスになるんです。なぜなら、泥を流したりとか、水の濁りがリセットされるからです。むしろ里山って人が適度に木を切ったり田んぼに水を入れたり抜いたりとかする、そうした適度な人為的なかく乱があって、環境の変化がリセットされる。ほっとくとただ単に一方的に遷移が進んで、独り立ちできるような生きものだけが残っていくことになるので、むしろ生物多様性が下がってしまうんですよね。こうした適度な人によるかく乱がむしろあったほうがいいことが見えたりします。こうした水環境も適度に水が抜かれたりしないと、生きものがなかなか住み続けられないと思います。
次はため池です。ため池は田んぼがあるところなら大抵あります。全国的には香川だったり兵庫の西のほうが多いでしょうか。雨が少なかったり、奥能登での珠洲みたいに里山は発展しているけど、あんまり川に恵まれてない地域だとため池が発達し、田んぼにとって重要であると同時に、生きものにとって重要な環境になったりしています。
そこでは、私の専門であるゲンゴロウが出てきたりします。ちなみに、ゲンゴロウを見たことある人はあまりいないんですよ。そうすると、現物を知らないので、地元の人から「ゲンゴロウおったぞ」と言われて見せてもらうと全然別物だった。よくそういうことがあります。大きいカエルは全てトノサマガエルとか、赤いトンボは全部赤とんぼとか、大きいトンボは全部オニヤンマとかなるかもしれないですね。
ただ、ゲンゴロウの他にもいろいろな水生昆虫がいるし、ゲンゴロウの中にもマルガタゲンゴロウとかいろいろな種類がいます。これも絶滅危惧に入っています。トンボでも全然違うものが出てくる。ため池とか湿地とかに抽水植物が茂っていると出てくる。アオヤンマとか割と希少種とされているものが出てきたり。またはオオルリボシヤンマ、やや寒冷なところにトンボが出てきたり、またため池といった水の中に、周りが山とか森との関係がありますが、クロサンショウウオが産卵していったり。クロサンショウウオは、割と止水、池とかにいて、石川からある程度の範囲ではそこそこ普通にいるかな。しかし、冬に産卵していることは知られていないと思います。そこで、能登で観察会やりました。2月の夜中にため池に行ってクロサンショウウオ見ようと。そんな時期に生き物いるの?とみなさんに驚かれました。行ったら実は結構活動して見られた。しかも、クロサンショウウオとい名前なのに白いといわれたりとか。
実は冬の間も水温は陸上よりは安定するので、意外と水の中の生きものを冬でも観察できたりするんですよね。また、ビオトープ水田では、湿地化した環境があれば世界最小クラスのトンボと言われているハッチョウトンボが見られたりします。1円玉に収まるサイズと言われています。そこまで希少種ではないですが、サラサヤンマという湿地性のヤンマが来たり、エゾトンボっていうマイナーなトンボが来てくれるかもしれない。
ある小学校の観察会を川で開催する予定だったのですが、川が少し増水して危ないということで、では水たまりでしましょうと言いました。最初がっかりされました。ところが、そこでやると途端に結構いろいろな生きものが見えました。さっきの田んぼの話と同じで、小規模な水域だったり一時的な水域にも、そういった場所に特化した生きものが来たりすることがあるんですね。オオヒメゲンゴロウというマイナーなゲンゴロウが出たりとか、うまくいくとホクリクサンショウウオが見つかったりすることもある。最初はがっかりしていた子どもたちも、あっという間に夢中になってくれました。もくろみどおりでした。ただ単に水がしたたっているだけの環境にも来る生きものがいるんですよね。
川でも観察会やってほしいという依頼が結構来ます。川でやるときれいなヘビトンボがいたり、またカゲロウの仲間、ナミヒラタカゲロウの幼虫がいたり、ヒトホシクラカケカワゲラの幼虫がいます。なかなかみなさん名前聞かないですよね。カゲロウははかないものだって言われます。成虫が1日ぐらいしか寿命がない。半日とか数時間のものもいるらしいです。ただ、その分幼虫の期間に時間をかけているタイプなんです。こうしたカゲロウがいっぱい見つかる。こうした水の生きものは魚にとっては重要な餌になったりするんですよね。魚とか水産資源を支えていたりします。
国交省とか環境省でやっている川の生き物調べという資料があります。見つかった生き物によって水環境はこんな環境ですねと言える指標になっている。観察会をして、サワガニだったりトンボはたくさん水があるところ、ここは澄んだ水なんだなとこういうことが分かったり、逆にザリガニとかエラミミズ、こうした生きものしか見つからなかったら汚れている水なのかなとか、そういったことが分かるかもしれない。
実際には単純に水がきれい、汚いという人の感覚とは違ったりします。必ずしもきれいな生きものがいればいいかどうか別の話です。たとえば川の上流だったらこうしたきれいな生きものにいてほしいのですが、逆に川の中流、下流なのにこんなきれいな水の生きものがいても、それはそれで不自然。むしろそうでなく、適度に栄養が入っている、決して澄んでいる水ではないけど、そうしたところに来てくれる生きものがいてくれるほうがむしろ健全だと思います。
環境に変なことが起きているのではないか、ある程度は見ることができるかなと思います。こういうのも見やすい生きものは知る手掛かりにもなったりしますね。さすがに上流なのにザリガニとか汚い水の生きものしかいないなら、ちょっとやっぱりおかしいことになっているんじゃないかなと考えられます。
そして、水の生きものは魚の餌として水産資源を支えたりしています。アユはコケを食べることが有名ですけど、実は水生昆虫も食べています。石川県ではゴリ料理が有名ですよね。カジカ、当然水生昆虫とか餌になる生きものがいないと住めないです。食文化とかそういったものにもちゃんと影響しているんですよね。
川でも上流の澄んだところと違って、中流の流れはあるが人里に身近なところでは、コシボソヤンマという流水性のトンボが出たり、コオニヤンマというトンボがいたり。鳴き声がきれいなことで有名なカジカガエルが出たりする。オタマジャクシ、流れのあるところに適応するせいか、口が吸盤になっています。さっきの川虫は平べったくなって爪が鋭くなって石の下に張り付くことができたりとか、適応しているんですよね。
そういった生きものがいたと思ったら、実は川にもゲンゴロウがいたりします。川に出るゲンゴロウは、池とか田んぼのゲンゴロウとある程度共通していたりはする部分はありますが、流水になった途端にがらっと種類が変わったりします。川でも下流であったり河口付近になると海と行き来しているものがいろいろ。中流、上流ですら、ちゃんと海とつながりがあって行き来している生きものがいたりしますが、海とのつながりも見えてくる。
能登町の九十九湾、のと海洋ふれあいセンターのところがアカテガニの産卵で有名ですし、観察もできる場所になっています。海沿いの田んぼだったらそういったものが来ることもありますし、イシガレイというカレイの仲間も見つかったことあるんです。海の魚じゃないの?と思ったら、やっぱり行き来していたりするんですよね。ボラだったり、調査でアジ捕れたこともあったかな。やっぱり海と行き来している。
今の時期、穴水ではアサザ漁が知られています。躍り食いで有名なシロウオがいたり。先日穴水の保育園の生き物観察に行く時に、川に行ってこれ捕ってきました。みんなのおじいちゃん、おばあちゃんはこういうのを捕ったりしているかもしれないんだよみたいなお話をしてきましたし、子どもはなかなかアサザ、シロウオのことは知っているわけではなかったとしても、大人はやっぱりよく知っています。
視点を陸上に変えてみると、樹液に来る生きものがいます。雑木林は田んぼとか、ほ場、里山の一部ですから、人が木を切るから光が差して、若い木がまた生えてくる、そうした環境がちゃんと適度に保たれる必要がある。人が何もしなくなると、よく昔の燃料に使っていたという落ち葉をかき集めるのをやめてしまうとキノコも生えなくなるし、新しい草も生えなくなってきますし、木を切らなくなると老木ばかりになってなかなか若返らなくなってします。そんなことも生きものからも見えたりします。カブトムシもやっぱり来ますし、鳥も結構います。シジュウカラだったり、ホオジロの子どもなどです。
ちなみに、私は津幡にある石川県森林公園を職場にしています。そこの建物のトイレ掃除に行っている女性職員が「きゃー」って声を上げたので見にいったら、クロサンショウウオがトイレに入ったとかありました。
当然里山とかの環境って、当然草原だったり花に来る昆虫もいます。ちなみにこれ長寿草って結構石川では希少種にされている植物ですけど、そういった場所にはハナムグリの仲間がこうやって花の蜜を吸いに来ることもあります。アブといっても別に人を刺さないですし、受粉媒介してくれているかなと思います。樹液にも来るし花にも来るようなチョウもいたりします。
こうした観察会をやってみた結果、最初は田舎の子どもでも田んぼに入ってなかったりしたのですが、積極的に自分から「田んぼを横断する」と言って、田んぼの中を歩いてくれる子どもが現れたりします。観察会に一緒に参加してくれた大人も夢中になったり、田んぼとか場所提供してくれている農家の方が「すごい励みになる」と言って、生きものに少し意識してみようかとか、いろんな影響が出たりします。いろいろな生きものがいて面白かったねって言ってもらえるには、しっかりした環境が、いろいろな環境が残って、そこにいろいろな生きものが残ってくれていることが重要だということが見えてくると思います。
当然、同じ水環境でも赤とんぼこれだけ種類が変わってくる。いろんな田んぼだけじゃ駄目なんですよとか、ため池だったり湿地だったりちょっと高層湿原っていわれている環境だったり、川で流水だったり、そうした環境が変わることで赤とんぼと一言で言っても、いろんな種類が見つかったりする。
生物多様性と環境の多様性
そうしたことから生物多様性、3つのレベルの生物多様性の中でも生態系の多様性、要はそれぞれ独立した環境だけどそれぞれ実は影響し合っていたりする。こうした生態系の多様性も見えてきますし、豊かな生態系とか環境が残ることで種の多様性、いろんな種類が出てくれる。種の多様性も見えてきますし、また遺伝子の多様性。実は地域ごとに微妙に違うんじゃないかっていうこともいつか分かるかもしれない。
見ていると、同じ種類でも能登と金沢って微妙に住んでいる場所違うような気がするなとか、地域によってどうも利用する環境を微妙に変えているんじゃないかなということが見えてくる時もあります。
そして、地形的なことも見えてくるかもしれない。石川県の6~7割は里山と言われていますが、能登になると陸地狭いですよね。震災の時、車による移動は大変だったと言われていますが、実は山は意外と低いし海に近い。前知り合いで山梨からよく出張で来られていた方からは、こっちのは山じゃなくて丘だと言われていました。川の源流域が海から数百メートルとか1キロしか離れてない。そんな環境でさえ川の源流域が発達しているのは珍しかったりします。石川県のそういう地形が見えてくると思います。
たとえば、富山を車で走ったことある方は、知らず知らず意識していると思いますが、石川県に比べて川が広いですよね。石川県は川は大体そんな長くないです。それ他の県の川に行くと途端に広くなったりとか、全然環境が変わってくる。生きものを見ていると全然違うんですね。なかなかデータ化したりとかできてないですが、魚とかゲンゴロウとか、富山にいたほうがむしろ見つけやすかったりする印象はありますし、流水性のトンボ見つけようと思ったら福井とかに行ったほうが石川県より見つかりやすい印象があったりします。いろいろな環境の違いが見えてくるんですよね。
こうした生きもの観察会を長く続けていくと、嫌な影響も見えてきたりします。定量的なデータではありませんが、とある小学校の同じ場所で観察を続けていたら、どうも生きものの種数が減ってきているということがありました。だんだん里山の管理が大変になって、続けたいけど田んぼは年取ったからやめるわってなって、ため池もどんどんヘドロ化してきちゃったんですよね。どうも生きものの種数もどんどん下がっていっていた、数も減っていた、そんなことがありました。
生物多様性の危機
冒頭の菊地先生のお話でも、生物多様性4つの危機という指摘がありました。そこから里山の生きものが見えることって結構あると思います。たとえば、開発、外来種、地球温暖化であったり里山の縮小だったり。分かりやすいのは人の影響ですよね、開発。ちなみに私の地元の横浜には意外と田んぼやため池があったりしますが、大体汚いです。開発によって環境は失われますし、川もやっぱり。石川県でも川は管理され過ぎています。
私の住んでいた横浜の地元は北部で自然が多いところでした。公園がセットになって池があります。ウシガエル、ブラックバス、ブルーギル、アメリカザリガニ、ミシシッピアカミミガメと外来種勢ぞろい。なんかすごいアメリカナイズドされた池でした。そうした外来種によって影響を受けてしまう。外来種についても国内外来種という問題もあったりして、北海道のトノサマガエルが入っちゃったとかいろんなことが起きているわけです。
植物も外来種がすごく入っていて、身近なものでも既に交雑してる、もしくは外来種が広がっていまする。実は外来種は双方向の問題なので、日本からもジャパニーズ・ビートルとか呼ばれちゃって、マメコガネとか、あと身近なクズがアメリカでは確かグリーンモンスターとかそんな呼ばれ方しているのとか、すごく大変なことになっています。
オオスズメバチがアメリカに最近侵入したことが話題になったとか、いろいろな話があるんですよね。温暖化したら、そこに適応していた生きものが減ると思いますし、雪解け水が減ると、どうも春の時期に水がたまる場所に水が減ったなっていうことも実感したことはあります。田んぼの害虫なんか、冬が雪が減るとむしろ生き残って、害虫として翌年に起こりやすくなったりする可能性あるんですよね。農業とか環境がほとんど変わってしまう影響が大きいと思います。
今回の里山に関しては、人の働き掛けがむしろ縮小することのほうが危険じゃないかと言われています。私が以前能登で見たことのある田んぼ、現役だった頃の田んぼですが、放棄されてあっという間にただの陸地化してしまう。これでもうカエルの住み場所は一つなくなったわけですよね。
私はゲンゴロウのことやっていて、みなさんからよく「手つかずの自然に行ったほうが生きものがいっぱいいるんじゃないか」って言われるんです。むしろ逆で、そういったところに行くと、せっかくため池があっても陸地化して跡形もないとか、そういうことが多いんです。むしろ適度に人の手が加わってほしい。ただし、加わるにしても農薬まいた直後に生きものが死んでたりとか、田んぼやる方にとっては仕方ない話かなと思うんですが、やっぱり近代化され過ぎると生きものにとって大変な環境になってしまっています。中干しとかの影響もそうですね。
ただ石川県、特に能登で起きている問題は過疎高齢化ですよね。農業の担い手がどんどん減って田んぼが荒れてしまう。しかも今回の震災によって、もっととんでもない影響が出ていると思います。地震の後、能登に行く機会ありましたが、比較的町中に近いところの田んぼは残ってくれていましたが、ちょっと奥地でやや離れたところは途端に耕作放棄地がぐんと増えたなんていうのがありました。これで生きものはどんどん減っていく。
ため池もほっとくとこうやって泥がたまって、最終的に陸地化しちゃうんですよね。こうしたことがどんどん起きています。地図を見ると、ため池のマークあっても、ずっと人が入ってないとこんな状態になっちゃったりする。放置された森とかこういった場所はただただ伸び放題になって若返らなくなっちゃう。こういったことがどんどん起きていくんですよね。私が保全にかかわっているマルコガタノゲンゴロウという希少種の生息地もまだ残ってはいるものの、管理されてないから、水がすごい濁ってきて、だんだん減ってきていることは見えてきています。
だから、本来は適当に水を抜いて流して、また違う水が入ってきてというサイクルがあってほしい環境だと思います。シャープゲンゴロウモドキの生息地になっている沼も、実はこれ沼地といっても元はため池だった。むしろ放置されて沼地化した時にシャープゲンゴロウモドキが結構来てくれたものの、さらに放置されたことで埋まりかけて、こうなると希少種の住む場所もまたなくなっていくわけですよね。こうしたことがどんどん起きています。
では、どうしたらいいか。また里山を活用してみましょうとか、そうした場所どんどん水を入れて変えてみましょう。たとえば、マルコガタノゲンゴロウとかそういったゲンゴロウが結構いる池でしたが、水が汚れてしまった時、うちの先輩がアドバイスしたのは、重機で泥かき出しましょう、と。なんか自然破壊しているようにしか見えないですけど、ちゃんとその後再生しました。ゲンゴロウ増えました。
みなさんにこれやってくださいとか言っても大変、そんな簡単にできるわけではありません。せめてこういう現状を知って、自分たちにできることを少しでもやれたらなとか、私でもできること、こういうことを伝えるだけでも違うと思っています。
生きもののことを伝えよう
こうした里山の生物多様性を知って、少しでもちゃんと周りに伝えてみようと意識してみよう。では、何をしたらいいかといえば、難しいことをしなければいけないわけではなく、身近な観察会が結構あったりします。こういったところに参加してみて、こんな環境が、里山が残ると、こうした生きものがちゃんといるんだって分かったり、学生にビオトープ体験してもらったこともありました。田んぼだった場所を掘り返して水がたまるようにすると、あっという間に生きものも集まるようになってくれたんです。ただそういった場所は変異も早くて、すぐにまた泥が入ってきて埋もれちゃうんですよね。学生をとかも、ここぞとばかりに働いてもらったらやっぱり即再生してくれた。
観察会をセットにすると、自分たちの活動でこんな生きものが増えるんだ、戻ってくるんだ、と分かると思います。観察会に地元の人にも入ってもらう、子どもらにも来てもらったり、いろんな周りの大人にもいろいろ巻き込んで参加してもらったり、そうしたところを里山歩きの場所にして、みんないろんな生きもののことを知ってもらう。
その例として、たとえば金沢市の浅野川は女川、犀川は男川と呼んだりしますが、清掃活動している団体があったものの、清掃活動の成果はなかなか見えづらい。たまたま知り合った方から、生きもののことを教えてほしいって言われて観察会やったら、川でこんな生きものがいるんだと実感してもらうことができました。東山でお茶とか踊りとか着物とかの活動やっている方たちが、こういった活動ができる。いろんな例があるんじゃないかなと思います。
難しいことじゃなく、とにかく生きもののこと知って見て触れる機会を持っていただけたらいいなというのが私から伝えたいことです。ありがとうございました(拍手)。
菊地:話もいいですが写真もいいですよね。すごいと思いました。私は大ざっぱで、カエルはカエルとかトンボはトンボという人間なので、野村さんのお話を聞き、きちんと自然を見なきゃいけないなとあらためて思ったところです。


【対話】
Aさん:最近よく外来種のことを考えるんです。特に今、大きな黄色いヒメリュウキンカがたくさん咲いていて、ヨモギとかを駆逐しています。私はできることとして庭にあるヒメリュウキンカをあるところは残して、あるところはむしっているんです。ヒメリュウキンカはキンポウゲ科で、一応毒性もあるので素手でやっちゃいけないって書いてあるんです。私は漆の仕事をしているので素手で取っています。私たちの庭とか周りの雑草にちょっと目を向けていただいて、外来種と在来種を考えていただければ。
ヨモギなんかは昔から日本にあって何十種類もありますが、ヒメリュウキンカとかいろんな在来種じゃないものが、在来種を覆ってしまう。葉っぱがぱーっと丸く大きくなるので、他の種が入れないし、とにかく根茎が付いていて強いんですよね。繁殖力も強くて、ほっとくと絶対増えるんです。そういうものに気を付けて庭の草むしりをしていただければいいかなと思います。
野村さん:外来植物、外来種のお話でしたけど、そもそもどれが外来種なのか、みなさん知らないで過ごしている方も多いと思います。身近な植物だと思っていたけど実は外来種だったりします。たとえば珠洲とか奥能登は外来動物少ないのですが、植物は田んぼ周りで平気でがんがん生えていたりするんですよ。そのことを全然知られていないです。名前知らなくても、現物を見たらこれヒメリュウキンカだとすぐ覚えていただけるかもしれないです。
Aさん:キンポウゲ科ですが、毒がすごくあります。子どもたちが摘んできたり、それから口にしたりしたらちょっと危ない植物なんですよね。オオイヌノフグリとかヒメオドリコソウはそんな毒性もないんでほっといても大丈夫なんですけど。
野村さん:私も植物そんな詳しいわけじゃないのですが、外来種はそもそも問題なのに、みなさんなかなか知る機会がないです。外来種に限らず、そもそも生きものを野外に放つことはしてはいけない。ヒメリュウキンカはおそらく観葉植物か何かによって広がったのかと思います。
Aさん:ヨーロッパ、特にイギリスにあるものがこちらに入ってきたんですよね。
野村さん:そもそも、野外に生きものを放してあげることがいいことだと思われているケースがすごく多いんです。私の職場でも、おじいちゃんが笑顔で孫の捕ったカブトムシを放しに来たという人もいます。別のとこで捕ってきたものだったりします。ニシキゴイを放したいんだけど、放す場所あるかという問い合わせの電話がかかってくることもあります。このくらい世間とのギャップが大きいんですよね。今は、一度捕ったものは最後まで飼わなきゃ駄目だといわれていますし、放流とかも全然意味もないし、むしろ悪影響だからやめたほうがいいという方向になっていますが、全然知られてないのはすごく残念です。伝えたいのですが、生きもののことに関心持ってない人にいっても、「あ、そうなの」でおしまいだったります。
Bさん:初めて参加しました。新潟県新潟市の日本自然環境専門学校から来ました。金沢生まれで今実家に帰ってきています。2年間、生物多様性とか農業について学ぶために新潟で1人暮らしして学んでいます。この会に参加してすごいいいなと思ったのが、農家さんと生物の専門家との間にすごい認識の差がある、生きものに対して認識の差があることをおっしゃっていたことです。
私も新潟県内で生きもの調査のイベントだったり、アルバイトで環境調査をしたりしています。その業務で石川県の放棄水田の調査もさせていただきました。とても貴重な生きものがいるのにグリホサート使ったり、ネオニコという強い農薬を使ったりする人もいます。用水路もとても大事で、コンクリートのU字溝を使うとトノサマガエルがいなくなるし、実はそこにアカハライモリもいたりします。そういうところも気にせずに整備したり、農薬を使う人が多いなと感じています。最近になってジャンボタニシ入れたとかも聞きます。まだ石川県も新潟県もないと思いますが、ジャンボタニシ入れて取り返しの付かないことになったと話もよく聞きます。
新潟県の佐渡はとても自然豊かでトキが生息しています。トキを保護するために農家さんも協力して「ふゆみずたんぼ」をしたり、田んぼの横にわざと水たまりを作るんですよ。それは特に稲を栽培するためではありませんが、ふゆみずたんぼを作ることによってトキが冬にもそこで餌を捕れる。農家さんも専門家と協力して生きものを守ってこうといういい取り組みをしているところも見てきました。
野村さんに質問したいことが一つあります。農家さんと専門家の認識をどうつなげていくか、どうすれば農家さんが生物多様性についてもっと高い意識を持ってくれるのでしょうか。野村さんとして、こういうことしたら良かったなとか、こういうイベントをやったら農家さんの反応もすごく良かったということがあれば、教えてください。
Cさん:金沢市内に在住しています。佐渡の農家さんが、農業にはあまり意味のない水たまりを作っていることはすごいことだと思いました。外来種の話も、ヒメリュウキンカもヒメオドリコソウも外来種と知っていましたが、きれいだなと思って写真を撮ったりしています。野村さんの飛んでるトンボの写真すごかったですね。外来種とは知っていますが、外来種も何とかなるんでしょうか。もうどうしようもない、受け入れるしかないのかななんて思ったりもしています。どういう態度を取るべきか、教えていただければと思います。
野村さん:とてもハードルの高い質問ですね。現場でやっていてもなかなか答えが出ない、私に限らずみんな苦戦していることだと思います。うまくいくとしたら農家の人たちに一緒に観察会とかに参加してもらって反応を見てもらうことでしょうか。子どもの反応はやっぱりダイレクトに伝わったりしますよね。
ただ、そこに来てくれるかどうかは別問題です。珠洲の小学校の観察会でも、必ず地元の農家に田んぼを提供していただいています。とても温度差があって、一緒に参加してくれて一緒に喜んでくれるところもあれば、「じゃあ分かった、使って」とか「そういう話があるなら」みたいな、「まあ」みたいな感じでそれ以上関わってくれないところとかもあります、そういうところで来てもらうのは難しいですよね。
やはり関心のない人に伝えるのはなかなか難しい。「虫、嫌」とかいわれて、もうそれで話がおしまいとか。この先が大事なのにできないとか。地道にやっていくしかないのですが、ただそれには限界があります。対症療法ではなく、根本からやってほしい、そもそも外来種持ち込んじゃいけないという考え方自体がスタンダードになって欲しいということがあります。
田んぼの周りに水を入れる場所は、佐渡で江と呼んでいるやつですよね。そういう田んぼがたまに残っていたりします。これがあるとトキも残ってくれたりしますので、すごくいいですよね。
菊地:江は能登にもありますね。私は生きものの専門家ではありませんが、農家の人たちと生きもの観察をやったことはあります。子どもが田んぼに来るのは、農家の人からすると非常にいいことのように思えます。高齢化が進むなか、生きもの観察すると子どもが来て、その親も来る。そういう人の流れができることについては、喜んでいる人が多いと感じたりします。
ただ一方で、農家の人のいろんな苦労とか大変さも理解して、お互いが理解しないとこういう問題は難しいかなと思います。農家の人にもいろいろな事情があるし、生きものを考える人の事情も当然ある。お互いがどうやって学んでいくか。
Dさん:外来種と文化、金沢の文化を考えたりもします。その典型的な例が、お茶をやっている人たちがお花茶時に、ヒメリュウキンカをよく使っていることです。夏になるとタカサゴユリとか。生けている人たちに「これ外来種じゃないですか」といったとしても「え、何ですか、それは。これは昔から使っているんですよ」といわれます。われわれが外来種といているものは全然受け付けられないです。ヒメリュウキンカ、すてきな名前じゃないですか。タカサゴユリもすてきな名前じゃないですか。何で使って悪いんですかって。ものすごく私も違和感をおぼえますが、やめなさいとはなかなかいえないです。おそらく、お茶花の歴史の中でずっと使われてきたものなので、難しいと私は思います。どういうふうにしてこのハードルを越えたらいいのかなと感じます。
野村さん:難しい質問ばっかりで試されているような気がします。一般の方たちにいってもなかなか難しいかなっていうのは正直なところです。これは飛び道具的なやり方と思いますが、もう生け花のトップの人たちに訴えるとか、そういうのじゃないと難しいのかな。そういう人たちが変わったら多分すごく変わってくれると思うんです。あとは、普段からもっと外来生物に関する教育がちゃんと広がってくれないと思います。
Aさん:たとえばチューリップも外来種ですよね。ラナンキュラスとか、ほんとに美しい外来種の植物を栽培してまで作ってますが、あれはあれでいいと思うんですよ。
逆に外来種を全部駆逐してしまったらいけないと思うんです。だからここはヨモギの里、ここはヒメリュウキンカの里みたいに、ちょっとヨモギも残るような配慮が必要だと思うんですね。ヒメリュウキンカはヒメリュウキンカで残すとこがあっていいと思うし、ヨモギはヨモギでヒメリュウキンカが生えちゃったらヨモギは全滅するから、そこだけはヒメリュウキンカ生えさせないとか、そういう頭で在来種を残す場所を作ってほしいと思います。
菊地:鹿児島の奄美大島にアマミノクロウサギという固有種、絶滅危惧種が生息しています。沖縄とか奄美地方には、ハブ対策として人為的にマングースが放たれた歴史があります。そのマングースによって、クロウサギが絶滅の危機に追いやられ、生態系が大きく変わりました。環境省は大変な資金と人員を投入して、つい最近、奄美のマングースを全滅させたと宣言しました。一方、人から聞いた話なので不確かなことではありますが、逆にクロウサギが増え過ぎて違う影響が出て来るという懸念もあります。生態系はいろいろなバランスで成り立っているので、何か退治したら何かいいという話でも単純ではないんじゃないか。もちろん、既存の生態系に大きく影響を与えるものは排除しなきゃいけないのですが、いなくなった場合また違ういろんな影響が出てくると思いますが、どうでしょうか。
野村さん:一つ問題解決したら次の問題が起きる。たとえとして大き過ぎる話かもしれませんが、歴史でいえば冷戦が終わって世界平和になるかと思ったら、今度は民族紛争やら宗教対立が起きちゃったとか。結局それを抑えたら違う問題が噴出しちゃうことがあると思います。とにかく問題解決はこれでおしまいではなく、次はこれだっていうのは常に対応し続けるしかないかなと思います。絶対に問題は起こり続けるということは考えておいた方がいいと思います。
Aさん:種の保存は大事ですよね。その種がなくなる、地球からなくなるっていうのは悲しいです。
菊地:そうですね。ここは越えてはいけないというラインはあるのでしょうが、この問題はそこ以外はかなりグレーゾーンみたいなところがあることでしょうか。だから一つの解決策をやれば全部が解決できるという話では決してないと思うんですよね。
野村さん:種の保存という話が出ました。一回いなくなると戻らないことが大問題です。いなくなってもいいということが続いていると、おそらくどこかで取り返しの付かないことが起きるんですよね。
ゲンゴロウでいけば、東京、神奈川は絶滅扱いになっていますし、地域レベルでは相当絶滅になっています。それはもう戻らない。こっちにもいるからいいというけど、それもいなくなるかもしれない。そもそもそっちにいるゲンゴロウと、かつて東京とかにいたゲンゴロウは別ものかもしれない。今、能登は地震で大変なんで、能登の生活とか文化がなくなるかもしれない時に、生きものの話かなんてとなるかもしれませんが、とにかく時間は戻らないことは少しでも知ってもらう必要があるかなと思います。
Eさん:金沢大学生命理工学類の学生です。奄美大島の話をしようと思っていたんですけど。そこで関連して。奄美大島の件は外来生物の根絶までは成功だったので、成功した理由を自分なりに考えています。やはりアマミノクロウサギみたいな象徴種がいたおかげで、行政だけでなくて市民も協力して取り組めた問題だったと思います。石川だと何が象徴種として使えるか分からないですけど、そういった象徴種が生まれると農家さんと専門家の意見の食い違いも減って、みんなで協力して環境関連の問題に取り組めるんじゃないかなと思いました。石川県でもし象徴種を作るとしたらどういった種なのかなと気になりました。
野村さん:ハードルの高い質問ばっかりですね。取りあえずいえば、これから放鳥されることになっているトキとかでしょうか。私の立場的にはゲンゴロウといった生きもの大事にしてほしいと言いたいのですが、やはり華のある生きもののほうが影響力強いんですよね。したがって、トキと表向きにはいっておきます。本音では違うものを推したいんですけど。
トキ以外で、生きもの保全に向けて何か華のある生きものを見つけようと思ってもなかなか都合いいのは思い当たりません。私のほうが聞きたいというのが本音であります。
トキのように田んぼの多様性と絡みやすいとか、ストーリーをつくりやすい生きものがいいと思います。魚だったら、こんなおいしいんだぞとか、そういう資源としてすごい大事なんだぞといえる。写真きれいに映えるものがよかったり、いろいろインスタ映えですかね。
ゲンゴロウはそうかっていうと、困ったなって。ゲンゴロウ見せて「ゴキブリみたい」っていわれることよくあります。よく見るとかわいいと推してもらえるとうれしいのですが、逆に変な盛り上がり方してもらっても、それはそれで取り返し付かない気もするので、なかなか推し方は難しいと思います。華のあるストーリーのあるもの、ただし裏でちゃんと違う、本当はこれも大事なんだということを進めていくことが大事かと思います。
Aさん:ギフチョウとか。
野村さん:ギフチョウも推しつつ、ギフチョウのためには、カタクリのためにはとかちゃんとそういう前座的なストーリーを作るのが大事かなと。私自身もこれがいい、どうしたらいいのかなっていうのは難しいですよね。
Fさん:野村さんほんとにご苦労様です。ゲンゴロウの研究をしている野村さんの姿は知っていますが、だんだんゲンゴロウが少なくなってきている。地域、社会、何が原因で少なくなっているのか、率直な感想を聞かせてください。もう一点は、今トキの話が出ていますが、トキの餌は何でしょうか。
野村さん:ゲンゴロウに限らないですけど、要は里山の管理が追い着かない、そういった人がいなくなっていることでしょうか。人の手が入って里山が保たれないと生きものが残らないこと自体が知られていないです。では里山をもり立てるにはどうしたらいいか。そもそも人がいないので、絶望的な気分になりますけど。
少なくとも、それを伝えていかないといけない。それに興味を持ってない人たちにもそれなりには伝わらないといけないという時、そこでちょっとつまずきかねないことはあります。トキ自体は田んぼであんまり餌を選んでないのではないでしょうか。トキにそんなに詳しくないんで。ただ田んぼに来る生きもの、餌としてのポテンシャルある生きものといえば、カエル、魚、多分餌になると思いますよ。イナゴも餌になるかもしれない。
先ほどの話と同じですが、アユとか水産資源も含めて餌生物が必要だっていう時、何が必要かなと、そもそもどこにどんな影響を与えるか、そういう情報すらなかなかなかったりするんですよね。
生きもの調査で紛らわしい種類が出た時、これ石川県の分布種でいいのかなとか結構迷うことがあります。そういった情報もやっぱり必要です。ベースの部分を上げていかないといけないと思います。
Aさん:クマとかイノシシとか、ニホンカモシカとかが、サルとかも害をもたらすようになりましたよね。里山が駄目になったことと繋がっていると思います。白山にスーパー林道が通ったりとかいろいろなことがあって、害獣がいっぱい出てきました。生態系が崩れたからだと思います。私たちの学生時代まではそんなことなくって、山行かないとクマに会えないという感覚でした。今は里まで出てきますし、夜は歩けないんですよ。そういう観点からも生態系の大切さをもっといってもいいと思います。
菊地:害をもたらす生きものが人間に近づいてきている話で、山を利用しなくなったという里山の危機と非常に密接に関係していると思います。
野村さん:クマやイノシシとか、さきほどのトキみたいなストーリー作る。華を持たせやすいとかと逆で、これはこれで結構伝えやすいかなと思います。ちょっと危機をあおるような感じになるかもしれませんが。去年は大問題になり、相当報道されて、里山と里の境界がなくなっちゃったとか、防げなくなったというか。そういう意味では伝えやすいのかなと思います。もちろんそれだけでは伝え切れないと思いますが、一つの方法と思います。
菊地:クマは人間を襲う可能性もある生きものなので、里山をどうするかという問題について、人びとが真剣に考えるためのきっかけとなる生きものと思います。金沢大学はよくクマが出ますから、怖いです。里山に対して、もう少し人間が入って、ここは人間の領域ですよという形の利用の仕方をしないとなかなか難しいと思います。
今日は、たくさんの生きものが登場しましたが、その大切さをどのように表現できるのでしょうか。全部が大事ですよといっても、なかなか難しいですよね。私がかかわっているコウノトリの場合、コウノトリは大事なのですが、一方野村さんみたいな方もいて、コウノトリだけではなく、こういう地味な生きものが大事なんですよと考えている人たちもいます。そうはいいつつも、コウノトリは生態系のトップであり、コウノトリが生息できることは、いろいろな生きものが生息できることという理屈は成り立ち、ストーリーを作っています。
野村さん:やはり日の当たるところだけではなく、それ以外のところも見てみましょうとか、そういったところは考えていきたいなとか、知ってほしい、伝えられたらなということは考えています。ただ、とても難しい。私だけではなく他の専門家も多分難しいと苦慮すること多いと思います。
菊地:もちろん専門家だからといって、必ずしも解決策持っているわけではありません。今回のように、現場の悩みをいろいろとお話ししていただけたら、一緒に考えることはできると思います。
Gさん:今回の震災があり、能登の里山、特に奥能登の現状はかなり厳しいものがあると思います。人がどんどん減っていくに当たって、里山もどんどん壊れていくことになっていくと、野村先生がライフワークでやっている生きものは、どんどんいなくなっていくだろうなと思いますが、現状はどんな感じでしょうか。
野村さん:まだまだ分からないことも多いです。海は報道されているので、みなさん知っているようにとても隆起しています。既に壊滅的な影響とかは出ているとは言われています。
里山とか水の生きものに関しては、長く見ないと分からないことではありますが、やはり里山が放棄されて住める場所がどんどん減っていく。ただでさえ先細りし続けていた生きものが、奥能登の過疎高齢化が何十年分ぐらい一気に進むのと同じで、生物多様性のほうも一気にダメージがくるとは思っています。たとえば、ため池とかでも地震と水害の影響でやはり堰堤(えんてい)が壊れていたとか見ましたし、水ためられなくなっているところとか。比較的町に近いところだったらそうでもないけど、ちょっと山里に行く途端、あれ、ここも放棄地になったのっていうぐらいにいきなり耕作放棄地とても増えているんですよね。
年を重ねるごとに一気にダメージが目に見えるようになってくるのかなと危惧はしています。ただ、まだまだ分からないことも多いので、ひょっとすると蘇生する場所、一部は湿地化して一時的に増える場所もあったりするかもしれません。それよりも減るほうが多いかな。長い目で見ていかないと分からないことだと思いますが、いいことはないと思います。
Gさん:情報提供ですけど、私も実家が能登で、週末は向こうに行って農作業とかの手伝いはしています。3月中ごろ、もうそろそろ田植えが始まりますので、農業用水の用水路の掃除を集落総出で行いました。周りを見ると活動しているのが、70代、80代で、最年少が私の53歳。結局若い人が誰もいない。森林とか山のほうも高齢化が進んでいるので誰も入っていかない。なので、野生動物がいっぱい出てくる。現状はそんな感じです。
70代、80代で動いている人たちは、一人一人いなくなっていく。そうすると田んぼとか結局なくなっていく。今、お米がないとかいわれているじゃないですか。きっとそういうことが続くと思うんです。作っている人たちがどんどんいなくなっていって、近い将来にひどいことになってくと思うんです。
Hさん:今、何をすればいいのかという話が多かったと思いますが、それのヒントを得るために歴史をさかのぼって、人びとは一体どういうことをしてきたのかを知りたいと思いました。里山の生物多様性がずっと下がっているというお話がありましたけど、歴史のどこかの段階にピークがあったわけですよね。その時の人びとの活動は生物多様性を上げるために効果的、生物多様性という観点から捉えてプラスの方向が持てたのかが気になっています。その当時の人たちの生態系に対する人為的なかく乱が、たまたま生物多様性の観点から見てすごく良かったという話なのか、生物多様性を上げることが人びとの暮らしを豊かにすることに直結していたからなのか。もしくは人びとが強い生物多様性への意識を持っていたのかとか。そういう背景をもしご存じだったら、知れるとありがたいなと思った次第です。
野村さん:少なくとも当時の人たちが生物多様性を意識していたことはないと思います。むしろ生活のために必要だからしていたことが、たまたま生物多様性に直結していった。または必要なものを守るためにはそういう作業が必要だった。たとえばマツタケは、適度に管理をしないと出ないです。したがって、必要だからやっていたのと、生物多様性に必要なものを守るためにやっていたことが結果としてっていうふうな、そこじゃないかなと思います。
昔も時代によっては木を切り過ぎて山がはげ山になっていた時代もありますので、昔が良かったかどうかもなかなか難しい。そして昔のデータがないのでわからないことが多いです。ただ生物多様性のためにというより、ちゃんと生活していたら生物多様性が保たれるというのが本来の理想なのかなとは思います。なかなか難しいことも多いと思います。
菊地:生物多様性という言葉自体が最近の言葉なので、そういう捉え方は基本的にしてなかったはずなんですよね。いろいろな生きものがいるという話はあったかもしれませんが。
今日は、里山の生きものについてたくさんお話ししていただきましたが、人間の暮らしとどのように関係しているのか、これから関係を作っていくのかという話だと思いました。ストーリーをどう作るかとか、そこに何か必要なのか、山に関わるとか田んぼに関わるとか、そのための理由みたいなものがないと、生きものが大事ですよ、生物多様性が大事ですよといっても、どうしようもない状況があると思います。
だから、里山の生物多様性は社会の問題だと思います。生きものの問題ですけど社会の問題なのです。どういうふうに私たちが、特に若い人たちが関わっていくかについて、考えなければいけないのかなと思いました。そんな感じで理解してよろしいでしょうか。
野村さん:大丈夫だと思います。
菊地:ありがとうございました(拍手)
今回も石川県立図書館の担当者の方に関連図書を集めていただきました。
いつもありがとうございます