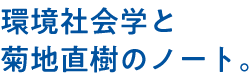第4回 のと里山里海カフェ(7/20)開催報告
第4回 のと里山里海カフェ
開催日時:2025年7月20日(日)13:30〜15:40
開催場所:能登町当目 当目地区多目的研修集会センター
テーマ:トキ、コウノトリと共生する地域づくり
参加者数:30名(一般参加者25名+スタッフ・関係者5名)
話題提供者である佐竹節夫さんは、兵庫県豊岡市コウノトリ共生課の課長として、そして日本コウノトリの会の代表として、人とコウノトリが共生する地域づくりをすすめてこられました。
佐竹さんさんを招き、「トキ、コウノトリと共生する地域づくり」というタイトルでお話ししていただきました。コウノトリが繁殖し、トキの放鳥を控えるなか、どのような取り組みができるのか。参加者のみなさんとともに話し合ってみました。
修田勝好さん(NPO法人 当目)
今日は「のと里山里海カフェ」を奥能登で初めて開催をさせていただくということで、本当にありがたく、うれしく思っております。
能登町当目地区は、奥能登の山の中ですね。今でこそ珠洲道路と能登空港ができていますが、昔は何かあると宇出津へ行って、そこから汽車で金沢へ出るという地域でした。
町野川の源流地、山田川の源流地、輪島に抜けている河原田川の源流地でもあります。源流地は、大体山の中、辺ぴな所ですね。1670年代には、この地域の石高が800石という記録が残っています。非常に米作りが盛んな地域だということは、この地図で見ていただければわかります。色付けした所が田んぼです。昭和40年半ばまでは、もっと山奥にまで田んぼがありました。昭和40年半ばの減反政策が始まった時、奨励金も出るということで、条件の悪い所を放棄して、だんだん山奥の田んぼが縮小をしてきました。それでも今現在、これだけ残っています。
条件は厳しいですが、非常に特徴のある米づくりを行なっていて、今に引き継がれています。
1つは「陰地(かげち)管理」です。日当たりを良くするために、山の一定の距離だけ、田んぼの人が管理する権利が昔から認められています。山主は、自分の山でありながら、田んぼのそばの地面は、田んぼの人の管理に任せると。場所によって、その長さが決められていました。日当たりのいい所、悪い所で距離が違っている。明治の個人所有が始まるまでは、地域で申し送りをしながら、それ以降は口伝えで、絶対に地域の人たちが守っていくと。他から入ってきて山を購入した人も、そこは手を出せない。当目へ行って山買ったら気を付けないといけないね、といわれています。地番としても、陰地地番が残っています。陰地の管理、それが最近は地域の景観にも非常に寄与していると考えられます。大規模な陰地がまだ残っているのは、珠洲道路の入り口の所です。きれいな所が残っています。
もう一つは「エゴ」とか「ソエ」というものです。段々の田んぼで、溝を切って、水が常にそこに滞留しているような感じになっています。山水を直接田んぼに入れているので、少しでも温めて米づくりをしたいという思いと、それから地面からにじみ出てくる水を遮断することによって田んぼを乾かして、米の生育を促したりと、いろいろな思いがありますが、最近は、生物多様性という点から非常に注目をされております。
生きものに詳しい方が調査していますが、希少種は、われわれが知らないだけで、至る所に目に付くような地域です。ハッチョウトンボにしろホクリクサンショウウオにしろ、この地域は、恵まれた環境になっています。
このような地域で、のと里山里海カフェを開いていただけることは、地元の者としてありがたいと思っております。今日はぜひ、皆さん、ゆっくり地域も理解をしていただきながら、またいろいろな活発なお話をしていただければありがたいなと思います。

蔭地
菊地
昨年度から「のと里山里海カフェ」を金沢で開催してきました。なぜ里山里海カフェなのか。第一に能登半島地震が起こった中でも、やはり里山里海が能登の復旧・復興基盤ではないかと思うからです。もう一つは対話ですね、いろんな人が話し合いをすることが大事なではないか。この二つを組み合わせているのが、のと里山里海カフェです。今回、奥能登で初めて開催です。修田さんにいろいろお世話になりました。みなさん、お越しいただきましてありがとうございます。
去年の11月、石川県の農業ボランティアで、たまたま来たのが当目でした。当目のことは、それまで正直知らなかったです。田んぼの泥やゴミをかき出す作業をしたのですが、修田さんが地元の担当で、作業をしながらいろいろお話しを聞いたんですね。作業終了後も先ほどの陰地とか、そういう話をいろいろ聞いて、生物多様性を大事にしている地域だと教えていただきました。1カ月後ぐらいに、中国出身の大学院生たちと再訪問し、案内していただきました。その時、のと里山里海カフェを当目で開催してみませんかというお話をさせていただき、今日の開催となりました。
先ほどの陰地の写真です。きれいに管理していますよね。蔭地って言われないとほとんど気付かないのですが、あらためて見てみると、きちんと人が管理していることが分かって、この地域が田んぼを大事にしていることがよく分かると思っています。
今日は、トキ・コウノトリとの共生がテーマです。トキの放鳥地が羽咋市に決定しました。能登にコウノトリが飛来していたり、そしてトキがこれから放鳥されますが、どう共生したらいいのでしょうか、どう地域づくりと結び付けたらいいのか。なかなか分からないこと多いのではないでしょうか。そうであれば一緒に考えましょうと、こういう機会をつくらせていただきました。
豊岡市からお越しになった、日本コウノトリの会の佐竹節夫代表から、コウノトリと共生する地域づくりについて話題を提供していただき、当目、あるいは奥能登におけるトキ・コウノトリと共生する地域づくりについて一緒に考えていただければと思います。佐竹さんは兵庫県豊岡市のコウノトリ共生課の初代の課長をされた方です。それ以前から、行政としてコウノトリの野生復帰をすすめられてきました。早期退職してNPOつくって、コウノトリの生息環境の整備に取り組んだり、国内外の市民のネットワークを作ったりされています。行政的なことも分かりますし、NPO活動を通して市民レベルのことも分かる方だと思います。よろしくお願いします。
佐竹さん
兵庫県の豊岡市から来ました。元は市役所の役人でしたが、早期退職をしNPO活動を始めました。豊岡の町をどうするか、豊岡のコウノトリを有名にして、豊岡を有名にしてやろうという思いがあったのですが、コウノトリがどんどん外に飛んでいったのでで、これは豊岡にこだわっていたらコウノトリはできないなと思って、日本コウノトリという会をつくりました。私は能登のことは全く分かりませんので、豊岡が今までやってきたことを説明させてもらって、対話ができればなと思っています。

【コウノトリ】
コウノトリはどんな鳥なのか。1つは水辺で暮らす渡り鳥ということです。もう一つは食性。植物は全く食べずに、生きた動物しか食べない。3つ目が大食漢、大飯食らいであることです。丸飲みできるものは何でも食べます。羽を広げたら、2メーターぐらいになる日本では最大級の鳥です。
渡り鳥ということについてです。東大の先生と中国とロシアの研究グループの調査です。アムール川の支流の流域と、黄河の河口付近と、長江の中流域。秋の終わりに南下して、長江の中流域で越冬して、アムール川に帰っていく。その中で、ちょっと好奇心のある鳥が朝鮮半島まで飛来し、さらにまた東方見聞録をやりたい鳥が日本まで来て、また帰っていったりします。越冬先の環境が良かったら、そこにとどまる性質もあったので、日本にとどまるコウノトリが少しいたと思います。
今は、中国でコウノトリ保護がとても進んでいますが、私たちが始めた時(1990年代後半)は、世界で2,000羽いるかいないかといわれていました。もう1万羽とっくに越えていています。
トキは佐渡島に550個体ほどいますが、外にあんまり出てこないですね。コウノトリは、大きく移動します。51という韓国で大歓迎された個体は、佐賀まで行って、2日後には長崎行って、鹿児島行って、岡山に行って豊岡に帰ってきて、こっち行ったりやっているうちに、長門から韓国に渡って熱烈歓迎を受けました。またうろうろしてて、沖ノ島経由で帰ってきて、最終的には島根県雲南市でペアを組んで繁殖しました。1日で400キロ以上は優に動く鳥です。
私たちのハチゴロウの戸島湿地のペアが生んだ第1世代から第4世代の子どもたちが、どこまで行っているのか。北海道から韓国から沖縄から台湾まで、どんどん散らばっています。渡り鳥ですが、一つのとこにこだわらないのが特徴です。
次、形態を見てみましょう。特徴が2つあります。1つは真っすぐな大きなくちばしです。先がとがっていますので、よくツルッパシっていわれます。ミミズよりも小さいものでも食べます。もう一つは目玉。私は歌舞伎役者の錦の絵のように、かっこいいと思いますが、これを怖いっていう方もおられます。こんなすてきな目をしていますよね。
なにを食べているのか。典型的には田んぼでドジョウを食べています。トノサマガエル、バッタ、ノネズミです。シマヘビか、アオダイショウかも分かんないですね。農家にとってありがたいのは外来種であるウシガエルを退治はしてくれますが、残念ながら、ウシガエルのオタマジャクシはあんまり食べないです。ちなみに、コウノトリが一番大好きな食べ物はウナギです。仲のいいペアでも取り合いします。これはスッポン。こんなもん飲めるのかと思ったら、飲んじゃった。これはヒラメですね。ヒラメって海の底にいますよね。くちばしが23から25センチです。それ以上深かったら、獲ることができません。ではなぜヒラメが取れたのでしょうか。韓国の済州島ですが、ヒラメの養殖場から逃げてきたやつを食べたのです。45センチぐらいで1キロほどあるナマズも食べます。今、飼育の中で与えている餌が、1日で大体500グラムです。1キロ食べたら2日間食べなくてもいいと考えますよね。ところが、この個体はどんどん食べる。3キロだの。肉食の鳥は、獲物がいたら追いかけて殺して食べる習性がある。ではメタボになるかといえば、ならない。みんな糞で出てしまう。たくさん餌場が要る、ちょっと手ごわい鳥です。
次に環境です。ロシアの生息地は地平線の向こうまで広がる大湿原。これだったらたくさん生息すると思えば、コウノトリはいまだに絶滅危惧種になっています。ここで問題です。国土が狭くて山が7割を占める日本に、なぜコウノトリは棲めたのか、棲めていたのになぜ絶滅したのか。今どんなことしているのか、というのが今日のお話です。
弥生前期の田んぼを発掘したら、コウノトリとサギの足跡が残っていました。コウノトリがいて、人間の足跡があるということは、弥生の前期に中国から稲作が入ってきて、日本全国に田んぼが広がり出したことで、コウノトリは日本での分布域を広げられたと思います。
田んぼは、米を作るだけの工場ではなくて、同時にいろいろな生きものを結果として生んで育てているアジア特有の湿地です。田んぼがあることが、コウノトリが生息可能であることの理由ではないか。もちろん田んぼだけではなくて、民家の裏山にアカマツの大木があり、そこで巣ごもりをして、田んぼに下りて餌を食べて子育てしていたのです。
ところが、田んぼが主要な餌場ということは、稲を踏む害鳥として、コウノトリはとても嫌われたんですね。豊岡でコウノトリをもう一度野生に返そうという時にも、総攻撃に遭いました。「あんなものはとんでもねえ」みたいな。経済の高度発展を経験した人たちですから、1粒でも、1俵に10トンを取らないと、一丁前じゃないという時代でしたからね。
明治時代になって狩猟の制度が変わったのですが、最初は何もなかったので、外国やら西洋人がたくさん来て、ばんばん撃ち出したりしました。明治25年、政府は『狩猟図説』をつくりました。富国強兵策を進めるためには、その鳥獣が農業を振興する上で有効有益か有害かって区別したんです。農業の振興に役立つもの、例えばツバメは野菜の虫を食ってくれるんで益鳥。ヒバリやスズメは、害虫は食べるけども、野菜も食べるから半々。こういう決め方を政府がしました。ツル、コウノトリ、トキは、ことごとく有害だから、何の役にも立たないと。銃で捕獲して、その肉を食べて、羽毛は利用せよと。だから、アホウドリなんか500万羽ぐらいが殺されて、みんな羽毛になって絶滅宣言されたんですね。
明治の30年ぐらいの間に、日本の多くの生きものが殺されてしまった。この図説を基にして、25年10月に規則を作ったのですが、これでどんどん殺されたんですね。明治41年にようやく狩猟法で初めて希少かどうかも判断基準になりました。トキとコウノトリとヘラサギが保護鳥になりましたが、もう時既に遅しという歴史をたどっています。
【絶滅から野生復帰へ】
問題はここからです。このように殺伐となっている日本の中で、では豊岡はどうだったのでしょうか。豊岡では当時、のんきにコウノトリ見物やっているんですよね。茶店をやって、芸者も連れていったなんていう話もありました。日露戦争に勝ったのは、コウノトリが営巣して、ひなを育てることができたからだと、戦地の兵隊に文書を送ったりしています。
日本中が役に立たんやつは殺せ殺せと言っていた時代に、能登もそうだったのではないかと思ったりします。政府の言っていること、そんなもん知らんわいやっていうのが能登もあって、独自の歴史、文化があったのではないかな。それが生き残っていたために、トキも最後までいたのかも分かりません。さっきの陰地ですね。うちの村でもいまだに誰もやるんですよ。そういう風習とか文化があることが豊かな印ですよね。
今の豊岡はこんな感じで盆地です。縄文時代に海進期があり、海がどんどん高くなって入ってくる。これの名残みたいなところです。全体が低いです。その田んぼを見てみると、こんな感じなんです。昭和30年代から40年代の初めぐらいの写真です、沼の中に田んぼがあって、田んぼに行くのに田船で行かなあかん。水路と田んぼが面一ですから、冬でも水路の魚が田んぼの中に入ってくる。その代わり、稲刈りも水浸しの中でやっている。こういう環境だから、コウノトリが豊岡で最後まで生息できたと考えられます。
ただ、水辺の生きものの生息には適していますが、人間にとっては大変だと。人間の、特に農家の我慢の上にコウノトリが生息できていたといってもいいかもしれません。一方にはいいけど、一方に悪いっていうのは、絶対長続きしないですね。第2次世界大戦後、豊岡の田んぼのほぼ全てを乾田にしたんです。水系は分断され、生きものは激減して、コウノトリは非常に住みづらくなった。
追い打ちをかけたのが農薬です。都会でこの話をしたらね、農薬を振っている農家の人が悪いってなりますが、みなさん、やっぱりそれは腹立つでしょ。何が悪いんやと。一生懸命真面目に農薬の農業をして食糧増産やっていて、こいつらが勝手に保護しているだけやないかってなもんですよ。
役所は、こういうことを考えずに、この鳥だけを保護しようとしたんです。今、獣医師さんの世界でよくワンヘルスといいますが、その動物の健康は、全体の環境によって影響されると。この考えが当時なかったんですね。1965年からは、捕獲してコウノトリを人間の管理下に隔離しました。しかし、どんどん死んでしまいました。当時の兵庫県の知事は、とても頑張ったんです。コウノトリの安住の地は、日本国中、一体どこにあるのかっと落胆していました。結局71年に野生絶滅したんです。
転機は、89年に飼育の中で繁殖したことです。旧ソ連から、若い個体をもらったことがきっかけですが、一つやっと風穴が空いたぞと。
2つ目は、菊地先生が勤められていた兵庫県立コウノトリの郷公園が99年にオープンしたことです。拠点ができて、どうするか。まず考え方です。コウノトリ野生復帰は環境問題だと考えました。人間がその環境を壊したから絶滅したのだから、その環境を取り戻す責任は人間にある。放鳥の前に国際会議とやると、「やっぱり私らが農薬を使っちまったんで、滅ぼしちまった」と話すおばあちゃんが、ぽつぽつといるんですよ。だから、農薬を使って滅ぼした、悪いことをしたみたいな、その意識が、相当野生復帰に力になりました。
となると、生きものだけにいいとか、人間だけにいいとかではなくて、人と自然が共生する地域社会を復活する、つくっていくということになっていきました。そのために何をするのか。2つあります。1つはコウノトリに徹底的にこだわって野生に返す。コウノトリにこだわる人。しかし、能登でも、繁殖したからといって、コウノトリにこだわる人は、そんなにいないと思います。もう1つは、コウノトリも暮らせる、イモリもゲンゴロウもオニヤンマもアシナガバチもみんなが暮らせるという、そういう地域にもう一度取り戻して持続可能にするというものです。コウノトリを守るということにこだわる人と、コウノトリも生物多様性の一つとして、広く農業を通じてやる人と、両方が必要だなと思っています。
では壊した環境をどうするのか。田んぼと水路の間にこれだけ段差作ったけど、階段作ったらつながるじゃないか。水田魚道です。水田魚道、豊岡では百何十基あります。壊したものを自然保護、保全するだけではなく、もう一度作り直す、ネイチャーポジティブだと、積極的に関わろう。今ようやくIUCNや世界のほうがいい出しましたね。豊岡はもう何十年が前から作り直そうとやっています。
稲を踏む害鳥という意識をどうするのか。豊岡では、徹底的に調べました。たまたま野生のコウノトリが飛来し定着していました。朝4時過ぎに集合して、何台かでコウノトリを追いかけて、下りた田んぼをみんなが見て、計数機で数えるんですよ。何歩歩いて何歩踏んだってやる。飛んで行ったら、そこの1台が追いかけていって、残った1台が写真撮って。兵庫県がまとめました。倒れた稲が起き上がってきたのかまで追跡調査までした。
結局、400歩で1株踏んだが、稲が育つまでにはほとんど害がなかった。密集植えなので苗が少々倒れても、風通しが良くなると農学者が説明してくれたりしました。いくら調べても、役所はうそを付いているか分からんという不審がありますよね。農家に委託するんですよ。「お金払うから、やってくれ」と。稲作への影響は、収量ではまずないです。コウノトリのイメージも変わり始めました。
その時は、1羽で大騒ぎしましたが、今は巣が25あります。でも、誰も害鳥とはいわないですね。それは、いい面と悪い面がありますが。やはり徹底的に調査すること。しかも、みんなでやることですね。科学的に評価してもらうことが必要だと思います。
もう一つの課題は、農薬で滅ぼしたのだから、それを使わない農業へとどのように変えていくか。役所も誰も先生がいないし、分かりませんでした。栃木から、民間稲作研究所の稲葉光國さんにきていただきました。すごい人でした。稲葉さんがいっていたのは、無農薬農業といえば、すごい汗かかんなんでしょ、雑草駆除にも。でも省力化ができる。収量も1反8俵いける。高付加価値が付く、と。
私は、この話にすぐ乗ったんです。何を省力するかといえば、結局、益虫に害虫を食べてもらうことです。例えばカエルにカメムシ食べてもらう。何かにウンカ食べてもらう。そういう食物連鎖の世界を田んぼの中につくるということでした。あとは技術です。この高付加価値はコウノトリが持ってくる。できたのが、コウノトリ育む農法です。
これは、JAS有機とは少し違います。安全なお米と生きものを一緒に育むというものです。高付加価値は、コウノトリの絶滅から復活の歴史、ストーリーを米に付けることで生まれました。ただ役所がいくら頑張っても、役所だけでは無理だと思います。県と県の農業改良普及員と農協です。大体、役所と農協って仲悪いんですよ。特に環境型の農業しようとしたら、農薬を売ってもうけている農協は、何で農薬を使えへんような農業を支援せんなんのやっていって、よくもめるんです。しかし、最初にコウノトリを野生に戻す返すことを挙げたら、市長もJAも、みんながわーっとその気になって一緒にできています。
先ほど、クモだのカマキリなどがたくさんいれば、害虫をどんどん食べてくれる。そういう世界をつくっていこうという時のスーパーマンがイトミミズでした。冬に水を張るのは、イトミミズとかユスリカとか、そういう微生物が生息できるためなんです。冬でも微生物動いていますから、それで土の中が、うごめかさせて、糞をたくさんしてもらって、とろとろ層を作ると。とろーっとなって、それを乾かすと硬くなって、下から種子が上がってこない。生きもの共生型の典型の一つです。
代かきして田んぼに水を入れると、カエルがそこに入ってきて産卵します。オタマジャクシになる。田植えから大体1か月後ぐらいに、一度中干しをしますよね。エラ呼吸しているオタマジャクシは干からびて死んじまうんです。「カエルになるまでちょっと待っとっちゃろうや」と。足が生えてから中抜きしよう、中干ししよう、と。これで大体10日から2週間です。うちの田んぼのオタマジャクシのほぼ9割がカエルになったぞと思ったら中干ししましょうねというのをやっています。中干し延期農法といい、補助金も出ています。
豊岡市は「コウノトリの舞」っていうのを商標登録したんですよ。これが貼ってあったら、経過がたくさん書かれていて、安全を行政が保証しています。だいぶ広くやっています。
コウノトリを2005年に放鳥しました。私の予想の何倍もたくさん人が来られたので、環境問題にたくさんの人の関心があったのかと思いました。最初、コウノトリ育む農法を始めた時は0.7ヘクタールでした。放鳥をきっかけにして、現在では512ヘクタールまで広がっています。豊岡市の水稲面積の約20%ぐらいです。これ以外に単純な減農薬だとか無農薬も取り組んでいますので、半分近くぐらいは環境配慮型になっていると思っています。無農薬栽培が増えてきていることはうれしいですよね。だけど、みんな高齢化しているから、先行きが怪しい。では、どうやって安定収入にするか。学校給食です。米、地元は食べないとね。豊岡はかなり前から米飯給食でしたが、無農薬米は高いので、減農薬米でした。熱心な農家の人が怒って、「うちらの子孫に、そんな米、食べさせられる」かと。試験的に無農薬米にしています。無農薬米はやはり高いんですよね。コウノトリ米の無農薬は慣行栽培米の2倍近くするんですよ。今、米代がすごい高いのに、さらに倍払うのかってなってしまいます。ふるさと納税だとか寄付だとかを導入して、また農家も手取りが少なくてもいいと。その代わり、コシヒカリじゃなくて、つきあかりっていう品種で作ることにしたんです。農家の手取りもちょっと減少してもいいとなり、全量、無農薬米になっています。これはぜひ能登でやってほしいですね、コウノトリがいる能登で。米飯100%から始めてもいいと思います。
田んぼは基本ですが、餌場として湿地も作らないといけません。やり方は4つです。1つは、田んぼを行政が買って、新しい湿地に造成する。2つ目は、休耕田や耕作放棄田を、補助金出したりして湿地化する。3つ目は、田んぼの中の一角、さっきのエゴですね。京都府の綾部市でもエゴで助かっています。意図的にもう一度どこかで掘り下げていく。4つ目は、河川敷を広く浅く掘り下げて湿地化にする。1番目の買収例が、私がいる「ハチゴロウの戸島湿地」です。18年連続で繁殖しています。ここのペアの子どもが、珠洲で今、繁殖しています。
豊岡市はどこまでが海で、どこまでが川か分かんないようなところです。この湿地を造ったことを契機にして、円山川と周辺湿地をラムサール国際条約に登録しました。淡水と汽水のせめぎ合い、エコトーンで一番多様性が多いところです。
問題は、すぐに草ぼうぼうとなり、自然にはいいのですが、コウノトリの環境ではないので、やはり田んぼ風にする必要があります。田んぼ風にするには草刈らないといけません。草刈るのは、私たちだけではとても無理なので、外からの人に手伝ってもらっています。これは土建会社が作業してくれたものです。人から人につながるようで、未来につながる写真だなと思って好きなんです。
小学生3年生の体験学習の中で自然体験をしますが、あんまり好きではありません。ここはコウノトリの環境のために働きに来さす、労力です、コウノトリに貢献しろってって。すると、やっぱり真剣になって稲刈り鎌やっているでしょ。刃物で怖いですけど、仲間同士が優しくなったり、根気強うやってくれるんです。
神戸のほうからわざわざお金を払って草刈りに来てくれる先生もいます。コウノトリのために働いてかいた汗は、隣の城崎温泉に入って、コウノトリ米のおいしいものを食べて、魚食べて帰る。こういうコースがあります。
やはり巣立ちするひなの様子を見ていたら、一生懸命立ち上がって生きようとしていますので、自然と手を合わすんですよね。私は、生きものを使う教育の一番いいとこなんかなと思います。
放棄田の湿地化です。全体がゆるやかな傾斜な棚田です。ここに勝手にくい打って、柵をしてやる。もう農業しないから、個人所有なんて言っとられへんと。ここの湿地全体がコウノトリの餌場やないかって、勝手にやっちゃう。でも誰も怒らない。外からウェルカムでいろんな人に入ってもらってやりましょう。能登はすごい災害があったとこですが、山裾からそのまま水を流さずに、山裾で一度水を受ける池を造る。少しずつ下流に流す。そういうことも、ちょっと実験的にやっています。この池は、すごいですよ。最初はアカガエルの卵でしょ、ヒキガエルでしょ、6月からはモリアオガエル。それを狙ってヘビやらいろんなものが来る。
休耕田のビオトープがあり、大規模な湿地を配置しています。これは補助金出しています、26カ所。問題は、生産性がある田んぼでも維持が難しいのに、こんな経済を生まない湿地を誰が管理していくのかということです。
川のほうは、浅く広く湿地にして、コウノトリが下りてくるようにする。9キロにわたって大々的にやっています。日本で絶滅したコウノトリをもう一度野に返す、野生復帰するんだ、それを通じて環境問題に取り組むんだっていうことを最初に大きな声出しておく。そうすると国交省も動き出す。一度予算が付いたら、毎年できます。今の復興の時に絶対やるべきですね。県の河川なんですが、井堰(いせき)があって魚が遡上(そじょう)できないでしょ。それを遡上できるようにする。円山川ですごい井堰を造りました。土地改良事務所が造ったのですが、いろいろな魚種に分けて、上る角度とか合わせていく。今の能登であれば、思い切って呼びかけたらできるのではないでしょうか。
それなのに、豊岡の円山川でもラムサール条約に登録されてから、水害対策として東日本の防潮堤と同じような堤防ができました。近くの人にとっては死活問題ですが、生きものから見たら、どうなの?となります。ちょっと油断すると、こうなっちゃうんですよ。復興も、ちょっと物言うのを小さくすると、こうなっちゃうと思いますので注意しましょう。
これは豊岡市内の今年の繁殖です。電柱のものもありますが、あとは人工巣塔なんです。今、人工巣塔を立てる活動しております。なぜ人工巣塔かいったら、まず、マツの大きい木がないからです。次に立てたら、事前にコウノトリの受け入れの準備ができるからです。いきなりコウノトリが飛来してきたら大変でしょ。事前に立てて準備する。コウノトリは、一度繁殖したら定着する習性がありますから、それを基にして落ち着いて地域づくりができる。だから、ぜひ人工巣塔、検討してほしいです。
これが巣塔です。輪っかを電柱にかぶせるだけです。日本コウノトリの会が今まで立ててきた所です。これは、かほく潟辺り。2年前に対馬に立てて、今年はとうとう韓国にも立てに行きました。
これが今年の繁殖です。珠洲も入っていますが、私たちの計算では68です。能登半島など石川県は、一気に4つなっちゃいました。ほんで、この利根川流域、ほんで、あとは佐賀、こんな感じになっています。兵庫県立コウノトリの郷公園発表で500羽を超えました。た。私は1,000羽が間もなく来ると思います。1,000羽が来ると、天然記念物だからと、近寄ったらいけないということではなくこと、もう違う世界になってくると思います。そこに向かって、いい議論ができればありがたいです。

対話
修田さん:2つあります。まずコウノトリをなぜ取り上げたのでしょうか。他にも取り上げるものがいろいろあるかと思います。それともう一つ、お米の値段1.9倍って言っていましたが、30キロ幾らで売れているんでしょうか。
佐竹さん:コウノトリの野生復帰を提唱した頃、コウノトリよりもトキのほうが有名なので、トキをやったらどうかっていう人もいました。私は「トキは絶対失敗する、豊岡には歴史がないから」と話しました。豊岡では、明治の37年からずっとコウノトリをやっています。地域とかを考えることは、嫌いも好きも、酸いも酸っぱいも、みんなでやってきたのです。豊岡の欠点でもあるし長所でもあると思います。これを他の鳥に変えたら、もうほとんど失敗だと思う。農家のおばちゃんが、農薬使っちまって、謝らんな、なんていうせりふは絶対出てこないしね。コウノトリと豊岡だけはぶれないようにやっていこうと。
お米の値段ですね。5キロで6,700っていったかな。2倍ほどになりますか。
修田さん:それを給食用で買い上げをしているんですか、それとも一般の小売店での値段ですか。
佐竹さん:末端の販売価格です。JAの買い取りは、もう少し安く設定されていますよ。
修田さん:佐渡のトキの話を聞いたら、JAの買い取りがあんまり高くなかったんですよ。
佐竹さん:生きもの共生型は、初期はどんどん補助出したり、中干し延期はこれで出したりっていうのはやっていますが、販売価格には全く。JAはJAでやっています。ただ、JAのいろいろな支援は、豊岡市の農林水産課が一緒にやっていますよ。生産者技術部会という生産者が研究会つくって、その事務局を農協が担っていて、いろいろな人に来てもらったり、現場で技術を磨くことは、行政と事務局ワンセットでやっています。農薬を使ったらあかんと言い出した最初は合鴨農法でした。合鴨農法の最初の時、JAの職員が事務局やっていましたから、あんまりけんかがなくて、持ちつ持たれつできています。
修田さん:買い取り価格は見てないですか?
佐竹さん:私は買い取りはあんまりみていません。だけど、2倍は、やっぱり高過ぎます。一般庶民はなかなか買えない。だから、買い手は富裕層になっちゃうんです。もともと稲作の文化がない沖縄とか、大手が買ったり、そこの買い取り額、相当あります。あとはもう個人取引です。私が提唱したいのは、子どもの学校給食。これ、絶対すべきですよ。パンなんか食べさしとったらあかん。
Aさん:私の妻情報だと、珠洲市の中学校だと月1パンで、能登町柳田の7年前のお話ですけど、1週間に1回パン食だと。
佐竹さん:1週間に一回をパンにしないといけない理由があるのでしょうか?
Aさん:子どもの希望とかもあるかもしれません。小学生が今いるので、聞いてみたいなと思いながら。
菊地:給食は、ご飯、パン?
Bさん:ご飯。
菊地:毎日ご飯?
Bさん:たまにパンが出る。
菊地:Bさんは白山市からですが、ご飯が多くて、たまにパンが給食に出てくるということです。どっちが好きですか、パンとご飯。
Bさん:ご飯。
菊地:ご飯、分かりました。
なぜコウノトリかといえば、共に暮らしてきた歴史があるということでした。
買い取り価格は、私の調べではJA買い取り価格は大体減農薬1.3倍とか、無農薬だと1.5から1.8倍ぐらいだったと思います。もちろん収量は減っていますが、農薬を買う出費がなくなります。減農薬だと、それほど収量変わりませんが、無農薬だと1割、2割ほど減るということはあります。
Cさん:歴史が大きいことは、なるほどなと思ったのですが、逆に、歴史がないとなかなか難しいなとも思いました。やりようとして、どんなことがあるのかなということがまず質問しようと思ったことです。もう一つはもっとシンプルな質問です。コウノトリという鳥自体で、踏み付ける以外に困ったことは、あんまりなかったんですか。例えば私は海の近くに住んでいるので、車の屋根にどんどん糞が落とされるんです。特に魚の時期によっては、いろんな種類の糞が付きます。他に何か困ったことがあったら教えてください。
佐竹さん:嫌なほうから先に言うと、やっぱ糞です、それと臭い。人工巣塔を立てる場合、そこも加減して計算します。しかし、電柱は民家のそばなので、そこに巣をかけると、そこで糞をします。糞と臭いとか。それと、鳥ファンの人がカメラ持ってきて、大型の車で農道を踏み付ける。農道が壊れたり、夜見られると気になって仕方がない。執拗に近くに来て見に来られるマニアの人が問題です。
歴史の話です。私がある地域でトキの委員で呼ばれた時、中国からトキの飼育の指導に来ていた女性がいました。トキの放鳥を将来したいという話になり、彼女が真っ先に質問したのは「ここに住んでいた歴史や経過ありますか」でした。その事実がなかったら、それは駄目だという。だから、生息していた事実と人間が育んできた共生の文化があることが一番だと。先ほど話したように、明治時代に資本主義が導入された時、能登では巻き込まれずに、何かあったんじゃないか。だからトキは生息できたのではないか。そうでないと、あんなきれいな鳥は一発で商売になっちゃいますよ。それを防いだ文化があるんじゃないですかね。それを掘り出すのは、みなさんの仕事ですね。
菊地:「私の地域にはコウノトリのような存在はいませんが、どうしたらいいのですか」というお話ですよね。なかなか難しい問題ですが、滋賀県のある地域では、農家の人たちと研究者が一緒になって、何が自分たちにとって大事な生き物かを考えたんですね。その結果、アカガエルの卵塊という物凄く地味なものになったんです。自分たちにとって、それがいることが大事だ、誇りだ、みたいな感じだと思います。
自分たちで地域を見直して、自分たちの地域にとって大事なものは何か、考える。それはコウノトリかもしれませんし、トキかもしれない。おそらく、アカガエルだと求心力、外からいろんな人が注目してくれることは、なかなか起こりにくいのかなとは思います。地域差があるので一般化することは難しいと思いますが、自分たちの地域で何が大事かということを、いろんな人が一緒になって考えることが非常に重要だと思います。
Dさん:私の先祖は能登町の出身です。昔聞いた話では、トキは稲を踏み荒らすから、トキなんて言わずに「ドウ」と言っていたと。ドウが踏み荒らすから、ドウドウドウっていうわけです。なぜトキがここで絶滅したかっていうと、話を聞くと、トキの肉は臭くない。コウノトリとかは。
佐竹さん:臭いです。
Dさん:トキの肉は臭くない。だから、戦後の食糧難の時代に、人間の食料になったのかなと思っていたりします。一つ聞きたいのは、能登はトキとコウノトリという2つの生き物が生息することになります。共存は可能なんですか。
佐竹さん:絶対可能です。同じ仲間ですよ。
Dさん:私の先祖が生きていた時は、コウノトリは兄貴で、トキは弟分だというようは話をしていました。今コウノトリが繁殖している所にトキを放鳥するっていうのも、一つ手とすることはどうでしょうか。
佐竹さん:けんかするかもしれませんよね。種のけんか、テリトリーの争い。今、佐渡で繁殖が減っているのは、けんかですから。巣の奪い合いです。トキ同士は、広いとこだったら、間隔を自分らで決めますから。だけど、狭い所で、コウノトリのほうが大型だし、たくさん食べるし、乱暴もんですから。種のトラブルのほうが大きいかも分かんないですよね。両方が増えてきて、まあまあこの辺で一緒にやろうやっていって話し合いが済めばいいですけど、最初からはちょっと、どうなりますかね。羽咋ではコウノトリの人工巣塔の下が放鳥予定地ですが。
Dさん:眉丈山はもともとトキがよく通ってて、最高5羽いました。
佐竹さん:どうなるかは、ちょっと様子見てみないと分からないですよね。案外至近距離でも、テリトリーをつくって仲良く暮らすかもしれません。コウノトリ同士でも、ハチゴロウの戸島湿地でも、250メーター先に巣があるんです。250メーターでうまく両方が子育てしています。だけど、何かの加減でけんかする時はありますよ。
Dさん:コウノトリとカラスは、よくけんかするって聞いたことがあります。
佐竹さん:カラスが怖いのは小さいヒナや卵を襲うことです。
Dさん:トキとコウノトリの関連性、悪くはないんだろうけれども、安心という。
佐竹さん:生息環境的には全く同じ田んぼ。トキのほうが小型の生きものを食べますが。動物同士の関係が、どこまで接点をうまくやるかっていうのは、彼らに聞いてみないと、それはちょっと分かんないかも分かんないですね。
先ほどの、トキは肉がおいしかったっていうのは、本当でしょうか。私は、肉食の鳥はみんな生臭くて、臭くておいしくないと思っています。カモがガンやら植物食べている鳥はおいしい、ニワトリも。コウノトリも、殿さんとか上級官僚が来た時の歓迎式とか、珍味で出した。おいしくはないけど、これ、地元の珍味だという使い方したのかもしれません。大衆の人がおいしいって食べたのかについてはちょっと疑問があります。
Eさん:稲を踏むことが嫌われていた原因でしたが、実際に調査をしたら、稲は復活して収量は守られたとおっしゃられました。石川県も、これから稲を踏むのではないかと懸念されます。これから研究機関とか行政も含めて調べる際、何かアドバイスがあればお願いします。
佐竹さん:役所が主導して、住民の人にも手伝ってもらって、早朝から日没まで追いかけていくしかないと思います。それをさぼったらデータにならないですから。先ほど話したように、車で追いかけて、田んぼに降りたらカウンター持っていって、何歩踏んだなっていうのはやらないといけないです。
Eさん:踏むという文句を言う人と一緒に調査をすればいいんですね。
佐竹さん:それが一番いいですよね。ここ何年も、私のところにコウノトリが踏むんだと苦情を言いに来た人はいないんですよ。よく考えてみたら、本当に被害は少ないことは分かったんですよ。大したことないと。でも、それだけでしょうか。みなさんも田んぼ作っていたら、例えば手植えする時に補植するじゃないですか。そこにコウノトリが降りてきて、トキが降りてきて稲を踏んだら、腹が立つと思います。何で腹が立つのかといえば、自分が植えた稲に愛着があるからですね。田植えの後も、1日に何度も水を見に行ったりしますよね。田んぼとか、稲への愛着は、愛情と憎しみと。ところが今は圃場整備で、鳥がここの田んぼに入っている、これはうちの田んぼじゃなかったしな、あいつの田んぼだしなって言っとるうちに、もう逃げちゃいますから。だから、田んぼへの愛着が今の営農組合、株式会社になってきていて、田んぼとか稲への愛着はどうなんだろうということはあります。むしろ憎たらしいと思うほうが、生きものへの関わり深かったのかなとも思います。これは逆説です。
Eさん:以前、のと里山里海カフェにトキの先生が来られたことがありました。その時に、杉の林で営巣している話がありました。もともとはアカマツとかに巣をかけていたと思います。
あともう一つ、14~15年前ですが、当目の近くにモミの木の林があって、そこにサギ類がコロニー作って大騒ぎになったことがあります。ただ、捕れないっていう話もあり、巣を下ろすわけにもいかないし、林を切っちゃったって話もあるんです。コロニーができた時、騒音とか糞の問題とか発生する可能性が無きにしもあらずだなと思っています。コウノトリは巣塔を立てるから、そこで制限はかけれますが、トキの場合は、どこに巣をかけるか分からないので、アイデアがあればお願いします。
佐竹さん:私たちが作る人工巣塔の巣台の直径は1.6メートルです。1.6メートルの台座ができる杉なんてないじゃないですか。2メーターの羽ばたきで帰ってくるためには、そして、1.6メーターの巣が載りやすいところは、マツになるんですよね。トキは小さいから、いろんな木の間にありますよね。しかも、コロニー作るでしょ。だから、そういう問題が起きるのかもしれませんね。コウノトリのように散らばってくれたらええんですね。
Eさん:けんかの話ですが、カラスの例です。通勤経路が宝達志水から七尾なのですが、途中で田んぼを見ると、田植えの時期で、代かきしますよね。それで、当然カラスとサギが仲良く餌ついばんでましたんで、餌が豊富にあれば、けんかはなくなるんではないかなと。
Fさん:羽咋でコウノトリが繁殖しているという話。
佐竹さん:繁殖はしてないです。集団でいます。
Gさん:集まっているだけなんですよ。今日現在、15羽います。
Fさん:気になるのは、羽咋でトキを放すことは決まっていますよね。それから、コウノトリが集まってきたら巣塔を立てたいとか。
佐竹さん:羽咋はもう二つ立っています。
Fさん:そこの所にもコウノトリが来ているのなら、トキを放すとバッティングしませんか。
Gさん:懸念もありますが、何もトラブってないんです。日本コウノトリの会が立てたわけでもないんですよ。羽咋の地域の方が、ここに立てますよと立てられた巣塔です。
Fさん:トキを放そうとしているコアのエリアがありますよね。そこの近くなんですか。
佐竹さん:近くでしたね。
修田さん:米穀店を経営されている社長がいらっしゃっています。販売をされている立場から見て、こういうような環境で取れたお米に対して、どのような付加価値があるのかお聞かせいただきたいです。
また、地域の希少種については、石川県の委員をされているIさんてが定期的に当目で調査をされていて、ご一緒させてもらっています。どういう生きものが生息しているのか、それがさらに今後、どういう環境をつくっていけば、さらに生息が維持されて、まだ繁殖できるのか。いろいろと希少な生きものが発見されていて、コウノトリと一緒になって、地域として今後、どういうふうに付き合っていけばいいのか。ただ付き合うだけでは、地域としては続かないと思うので、地域づくりにつなげていくために、どういうようなこと考えていけばいいのでしょうか。
Hさん:金沢で米穀店をしています。10年以上前になりますが、福井県越前市の武生のコウノトリ米を扱っていました。ある理由で、もう扱えなくはなったのですが、それなりに需要はありました。そういうものが地元にもあれば一番われわれも販売もしやすいです。
菊地:どのようなお客さんが買うのでしょうか。
Hさん:電話での問い合わせだったり、インターネットだったりしますので、富裕層なのか、農薬とかを気にされる方か、ちょっと不明なとこはあります。需要としては十分あったかなと。絶対数も少ないので、そんなに量は入ってこなかったのですが、そういうものが地元にあればなとは探してはいました。
菊地:生き物米は、ちゃんと需要があるんですね。
Hさん:あります。
菊地:越前のお米を取り扱った理由はなんでしょうか。
Hさん:最初は問い合わせがきっかけでした。それから少しずつ扱ってくうちに、少しずつ量が増えてったと。
菊地:当目のお米を食べました。とてもおいしかったのでブランド化できると思います。
修田さん:慣行米でしたが、さらにまた上位米もあります。
菊地:今、米の値段上がっています。その状況からすると当目のお米は安いです。もう少し値段を上げてもいいのではないかと思うのですが。
修田さん:こういう時にこそ頑張って値段を上げないで、お客さんの助けになる。将来につながるかなと思いますので、今年も上げる予定はないです。
菊地:お米については、ブランド化うまくできれば需要があるということですね。米不足となり、お米の大事さが改めて認識されていますので、どのようにストーリーをつくりブランドにできるか。
佐竹さん:豊岡でコウノトリ米を最初に始めた中心人物が言っていたことは、「わしら農家はすごい楽や」と。「役所のおかげで先生が来てくれて、JAが事務局やってくれて、価格も、こういう米作ってますよいって農家がいわんとあかんのやけど、そんなことをいわなくても、行政がみんなコウノトリのストーリーをやってくれる」。「農家はこう頑張ってて、こんなんしてるん」だと。こういう社会を今築いてるということを、役所がコウノトリ、コウノトリといってくれるから、それが価格に反映されて、どんどん高なっていく。能登でも役所が頑張って、いろいろPRしてもらったらいいと思いますけどね。
菊地:今日は残念ながら役所の人は、来てないでしょうかね。
豊岡の場合は、行政主導型でストーリーを作って、もちろんいろいろな人がストーリーを一緒に作ってきたのですが。こうしたことどこの地域でもできるかということは課題としてあると思います。
Iさん:ホクリクサンショウウオが当目にいるのですが、そういった水の生きものに興味があって、2年ぐらい前から当目でお世話になっております。当目では、希少なものから比較的普通に見られるもの、いろんな水の生きものがいます。ビオトープは、トキとかコウノトリの餌場になるかもしれません。そういった場所を作ることによって、希少な生きものも増えていく予感がしております。
その一方、作ったら、どうやって維持をしていくのか。地元の方と考えていかないといけないと思っています。よそから人を呼んで維持管理をしていくやり方があるというお話がありましたが、そういったやり方も一つと思っております。
コウノトリとかトキも希少な生きものですが、それ以外に水の中で小さな希少な生きものがいっぱいいます。トキとかコウノトリがやって来ることによって、そういった生きものに与えるダメージはどうなのでしょうか。豊岡では、そういった議論は出なかったのでしょうか。
佐竹さん:今、出ています。広島県の中国山脈の中にコウノトリが繁殖しています。今日のような集まりに呼ばれて行ったんですよ。ナゴヤダルマガエルを一生懸命保護している人が「とんでもねえ」「来たらカエルを真っ先に食べちゃうじゃねえか」と怒っている。
僕は、そういう議論が一番好きです。カエルの保護の人は、絶対そうだと思うし。コウノトリなんか来んように、いろいろしたれと。いろいろな生きもののファンの人がいますが、最後は接点ありますから、まあまあこの辺で妥協しようかというか、コウノトリがそこに行かんように、こういう保護しようとなってくると思います。その場で話し合うことをする必要があると思います。そうしないと、どっちの不満も解消しないですから。
Iさん:私はトキの放鳥に反対ではありません。今までなかったことなので、少し気になっています。
菊地:トキの放鳥やコウノトリの飛来によって生態系が変わる可能性があるというお話ですね。
佐竹さん:研究者の方が、どんどん生きもの食べるから多様性が損なわれるという話をしています。私はそんなわけはないだろうと。コウノトリが食べる量はどれぐらいでしょうか。減らないと考えています。
修田さん:昆虫標本にすると売れるという話もあります。外からたくさん人が来て、環境いいと来て、そういう人たちが紛れ込んだ場合、どういうふうにしていけばいいのかな。黙ってそっと隠していくのがいいのか、オープンにするがもいいのか、他に方法があるのか。
Jさん:石川県立大に所属しています。佐渡でトキの研究にも関わっております。今のお話、すごく重要です。希少種を守る時に、外から人を入れると密漁されることがあります。かといって、秘密にして守ろうとすると、人手も足りないし、そもそも注意も払ってもらえなくなってしまいます。水辺の昆虫だと思うんですけど、守るために、売買しても価値がないようにするんですよ。田んぼで捕まえたよって時に、みんなでペイントして、継続観察しようと。情報を開示しながら守る。
菊地:狩猟価値をなくすということですね。ずいぶん手間かかるのではないですか。
Jさん:だけど、自分たちだけで守れない時にはそういう必要もあると思います。あと、環境教育として考えてもいい。もっとオープンにしないと駄目なんですよね。自分たちだけで守るということは、ちょっと難しくなっていると思います。
菊地:担い手がいない中、同じような悩みを持っている人、地域も多いと思います。オープンにして、いろんな人を巻き込みながら、教育に活用するとか、あるいは狩猟価値をなくす方法ですね。
佐竹さん:でも、われわれがやったら、法律とか条例に引っかかるとかないのですか。
Jさん:そこも含めて専門家に相談して、申請すれば通りますので。
菊地:地元の人からしたら、希少な生き物と共存していくことも負担になるところもあるということですね。オープンにしながら、外の力も借りていく。
少し話を戻しますが、魚の研究者だったら、魚をコウノトリの餌というなと思っていたり、カエルを好きな人は、餌としてカエルを見られることに違和感を持っていたりします。それぞれの人たちが愛着やプライドを持っています。
コウノトリだけとかトキだけがという話ではなく、それぞれの生きものが大事だし、それぞれの生きものに思いがある人たちがうまく付き合っていける形になったほうがいいと思います。いろいろな人が来て、地域が元気になるようなアイデアがあればぜひ。
Eさん:当目に興味湧きましたとなれば、田んぼの管理とか、イノシシ用の柵も張らないといけないとか、農業的にも守っていかないといけないことがたくさんあります。石川県では農村ボランティアを募集しています。トキが来たので、トキの田んぼを守るためにみんな来てくれというように、正式に募集をかけて、県庁からバスで人を乗せてくることもできます。トキが来たことをきっかけにして、県に相談するなり、集落として気持ちがあれば、そういう時は顔を出します。ぜひとも手を挙げていただければと思います。
ボランティアも高齢化が進んでいるので、高校生から参加できるシステムができればいいと思っています。
菊地:豊岡では企業の社会貢献活動をうまく利用していました。大学でもボランティア募集できます。
広島県の北広島というところで聞いた話です。子どもに色々な活動をしてもらうのですが、お金を稼ぐ活動をさせるんですね。社会の中で、人が動けばお金も動く。だから単に無償労働で何かやるのではなく、何か活動をしたら地域通貨をもらえて、それを子どもたちが何を使うか考える。お金教育も兼ねて、里山活動をする。子どもの頃から、お金を稼ぐことはどういうことか、それを使うことはどういうことかを考える。農村の生物多様性を守るための小さな経済といっていいのかもしれません。
Jさん:地元のみなさんにお伺いします。この地域の魅力、守りたい自然って何でしょうか。それがゴールだと思うんですよね。希少種、珍しいものいます、その価値を見出すか見出さないか。希少種ではなくて、この美しい風景残したいとか、当目の川を、このままの姿でまた孫に伝えたいとかですね。何か大事にしている、思い出になることとか。そういうのをお手伝いするのは私たちの仕事かなと思っています。
菊地:私たちよその人が押し付けるのではなくて、地元の人が大事なところ考えていく。
Kさん:当目は、あの有名な猿鬼伝説の発祥の地です。
修田さん:一人一人違うと思いますよ。
菊地:多分違いますよね。話し合いの場をつくってもいいですよね。
Jさん:それをみんなでまとめていくと、すごくいい。
修田さん:身内だけで集まると、飲んで終わっちゃいます。みなさんのお力を借りて、引っ張り出してもらえれば。
菊地:これは次の課題としたいと思います。地域の人たちで大事だと思うもの、みんなで残していきたいものは何か。それをどうようにしたら、外の人が関わりを持ちながらできるかを考えていく場を次につくってみましょうか。
修田さん:今日は初めてのことで、私自身も正直、内容がよく理解できていませんでした。今日でイメージが分かりましたので、なるべく地域の人たちが多く関わっていけるように、促していきたいなと思いますので、ぜひまたよろしくお願いします。
菊地:よろしくお願いします。それではどうも皆さん、どうもありがとうございました(拍手)。