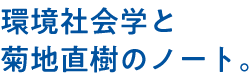日本鳥学会で自由集会開催
日本鳥学会・自由集会「バードウォッチングにおける『利用と保全」の循環」を開催
2年前、金沢大学で開催された日本鳥学会の自由集会で発言したことにより、ネットワークが広がり、昨年は報告者、今年は「バードウォッチングにおける『利用と保全』の循環」の企画者になってしまいました。会員でなければ企画者になれないため、環境社会学を専門とする私ですが日本鳥学会に入会。
以下、集会の簡単な報告です。
松井淳さん(Sicklebill Safari)のパプアニューギニアのお話では、バードウォッチングにより狩猟圧が弱くなったとのこと。二重価格や属人的な意思決定など、色々興味深かったです。松井さん曰く「パプアニューギニアは最後に行ってみたい場所」という人も多いとか。最後でなくていいので行ってみたいなあ。
島田哲郎さん(宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団)からは、伊豆沼・内沼のツアーの話。底上げを目指したもので、参加者の満足度は極めて高いものの採算性がないことが課題。ツアー内容や費用設定などをどうすればいいのか?
須藤明子さん(株式会社イーグレット・オフィス)からは、伊吹山のイヌワシのカメラマン問題のお話。極めてマナーが悪い人たちが集まり、生態系への影響もみられた中、秘匿から見せる方針に大転換。公開したことにより共感が広がり、行政なども参加した対策により、マナーが悪いカメラマンがいなくなり、イヌワシを解説するツアーを実施するようになったとのこと。この大きな転換もたらした力学はどのようなものか?
高橋満彦さん(富山大学)からは、資源管理の視点から法政策について解説していただきました。撮影・鑑賞は奨励すべき活動であるが、では生態学的課題や社会経済的課題もある中、どのようなものが認められるのか。それはグレーゾーンにある。法律は大事だけど万能ではないんだなあと再認識。
各報告の後、対話。時間が押し30分しか時間がありませんでしたが、多くの人からさまざまなお話をいただきました。
関係者のみなさん、参加していただいたみなさん、ありがとうございました。